お電話でのお問い合わせ:018-864-4431
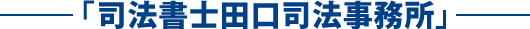

(当事務所の取扱業務)
① クチコミトラブル解決対策
(削除申請、開示請求、仮処分申請、損害賠償請求、刑事告訴)
② 簡易裁判所訴訟代理、前記の法律相談
③ 地方裁判所等へ提出する裁判書類の作成、裁判書類作成事務の相談
クチコミサイト・掲示板・SNS等に個人・企業(以下、「企業等」という。)の誹謗中傷を書かれた場合の対処法
クチコミサイトにおける悪評や誤解を含む投稿は、企業等の信頼と評判を大きく損なう可能性があります。特に、匿名での投稿が多いインターネット上では、企業等が迅速かつ適切に対応することが求められます。
こうした状況において、法律専門家(弁護士・司法書士)の支援を受けることは非常に重要です。
(目次)
1 クチコミサイト対応の重要性
2 法律専門家によるクチコミサイト対応
1 クチコミサイト対応の重要性
(1)法律専門家等の相談で対応を始める理由
クチコミサイトでの悪評や誤解を含む投稿は、被投稿者の評判を大きく損なう可能性があります。このような問題に対処するためには、法律専門家への相談が重要です。
① 法律に基づく正確な対応
法律専門家は法律に基づいて、どのように対応すべきかを指導します。例えば、誹謗中傷がなされている投稿の「削除請求、開示請求の方法」、「裁判所への仮処分命令の請求(開示請求・削除請求)」、「不法行為に基づく民事上の損害賠償請求」、「刑事告訴(侮辱罪、名誉棄損罪、威力業務妨害罪等)」などです。
② 証拠の保全
法律専門家は、問題の投稿に対する証拠を適切に保全し、必要な法的手続を進めます。
③ 迅速な対応
クチコミサイトでの問題は迅速に対応することが求められます。法律専門家の介入により、迅速かつ効果的な対策が可能となります。
法律専門家に相談することで、被投稿者は法律に基づいた適切な対応を行い、評判を守ることができます。これにより、ビジネスの継続的な成長をサポートします。
(2)企業等がクチコミサイト対応を行うべき理由
クチコミサイトの評価は、現代のビジネス環境において非常に重要です。ポジティブなクチコミは被投稿者の信頼性を高め、新規顧客を引き寄せますが、ネガティブなクチコミは逆の影響を及ぼします。
① 顧客信頼の維持
ネガティブなクチコミが放置されると、顧客の信頼を失う可能性があります。迅速に対応し、誤解や事実誤認を訂正することが重要です。
② ブランドイメージの保護
悪評が広がる前に対応することで、ブランドイメージを保護することができます。
③ 法的リスクの回避
誤解や事実無根の情報が拡散されると、被投稿者は法的リスクに晒される可能性があります。法律専門家と連携して、適切な法的対応を行うことが求められます。
2 法律専門家によるクチコミサイト対応
(1)初期調査から損害賠償請求まで
法律専門家による迅速な削除対応は、被投稿者の評判を守るために重要なポイントです。適切な手順を踏むことで、迅速かつ効果的に問題を解決することができます。
① 初期調査
法律専門家は、問題となる投稿の内容を詳細に調査します。この調査に基づき、削除請求の根拠を明確にします。
② 削除依頼請求
問題の投稿が、「名誉毀損罪」や「誹謗中傷」に該当する場合、法律専門家はクチコミサイトを管理ないし運営している事業者に対し「投稿の削除」を求めます。削除請求フォームないし通知書には、「削除を求める法的な根拠」と「具体的な要求」を記載しなければなりません。また、投稿者が明らかに特定されている場合には、投稿者に直接通知を送ります。
③ 発信者情報開示請求
削除要求に応じない場合、法律専門家はプロバイダに対して発信者情報の開示を求めることができます。これは、投稿者の情報を特定し、必要な法的措置を講じるために行われます。
④ 仮処分の申請
任意による削除要求が拒否された場合、法律専門家は「裁判所に仮処分命令(開示請求と削除請求)」の申請をします。仮処分命令が出されると、裁判所は投稿の削除を命じます。
⑤ 仮処分命令の発令
裁判所から仮処分命令が発令された場合、仮処分命令に基づき、ウェブサイトの管理運営者は「投稿を削除する義務」を負います。
⑥ 損害賠償請求
削除対応と併せて、「損害賠償請求」も重要な事項です。被投稿者の名誉を毀損する投稿にしよって生じた損害について、投稿者やウェブサイトの管理運営者に対して損害賠償を求めることができます。損害賠償請求は、被投稿者の経済的損失や精神的苦痛に対する補償を得るために有効です。
⑦ 刑事告訴
投稿内容が「名誉棄損罪、侮辱罪、威力業務妨害罪等」に該当する場合もあり、刑事告訴の対象となることもあります。
(2) 裁判手続を通じた削除請求
裁判手続を通じた削除請求の方法には、「仮処分の申立」と「通常訴訟」の2つがありますが、通常は「仮処分の申立」が行われます。
(理由)
A 仮処分の申立により、仮処分命令が出されるので、スピーディーに削除請求の目的を達成することができる。
B 通常訴訟では、判決までに時間を要するので権利侵害が拡大するおそれがある。
(3)「情報流通プラットホーム対処法」(旧:プロバイダ責任制限法)
情報流通プラットホーム対処法は、プロバイダ等の「損害賠償責任の制限」、「発信者情報の開示請求」及び「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」について定めた法律です。
①「情報開示請求権
名誉毀損罪や著作権侵害が認められる場合、被害者はプロバイダに対して投稿者の情報開示を求める「発信者情報開示請求」を行うことができます。
②「違法なコンテンツの削除」を求める権利もあります。
* ただし、削除を義務付けるものではありません。
③ 「情報流通プラットホーム対処法第3条」
「権利侵害を知っていた場合、ウェブサイトの管理運営者に責任を問うことができる」と定めています。