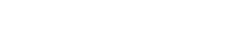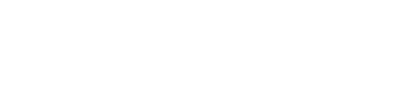刑法における故意
犯罪事実が生じることを認識し、予見している心理状態を「故意」といいます。
刑法は、「故意がなければ犯罪とはならない」ことを定めています。
条文を見てみましょう。刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定しています。
犯人は、自分の行為によって、犯罪となる事実が発生することを知っていなければなりません。
これは刑法の大原則なのです。
ただし、例外として(故意はなくても)過失があるときに処罰される場合があります。刑法は38条1項ただし書で、「法律に特別の規定がある場合」には、過失犯の例外を認めています。
同じように人を死亡させた場合でも、故意がある場合は殺人罪(刑法199条)で、上限は死刑、下限は懲役5年ですが、過失の場合は過失致死罪(刑法210条)で、50万円以下の罰金となります。
このように過失犯の法定刑はかなり軽くなるため、故意があるかどうかは大きな問題となります。
故意は行為の時点で認められなければいけません。しかし、犯罪となる事実が生じるのは、行為の時点からみると未来のことであり、行為者にとって犯罪となる事実が生じるかどうかを予見することは難しいことでもあります。
例えば、至近距離からピストルを発射する際、きっと銃弾が命中して相手は死亡するだろうと思っている場合には、殺人罪の故意を認めることができるでしょう。
しかし、『ウイリアム・テル』で我が子の頭の上に乗せたリンゴを矢で射ようとしているテルには、殺人罪の故意を認めてもよいのでしょうか。この時テルは、矢が我が子に命中するかもしれないということを認識し、またそのことをある程度の可能性をもってあり得ることと予見しています。
このように、結果をはっきりと予見しているわけではないが、あり得ないわけでもないと認識している状態を「未必の故意」(みひつのこい)と学問上呼んできました。犯罪のニュースを報じる新聞記事などでも目にすることのある難しい言葉です。
この未必の故意が問題となった判例として有名なのが、盗品有償譲受け罪(他人が盗んだ物を買い取る罪。刑法256条2項)についての判例です。
最高裁判所は、「必ずしも買った物が盗品であることを知っていなくても、盗品であるかもしれないと思いながら敢えてこれを買い取る意思(未必の故意)があれば足りると考えるべきである」として、未必の故意を確定的な故意と同様、「故意」と認めています。
つまり、ある犯罪事実が生じることを「あり得る」として認識・予見し、それを容認・認容した場合には、故意(未必の故意)があると考えるのです。
この先には、「未必の故意」と「認識ある過失」の区別という複雑な議論がありますが、それはまたの機会に。
(佐々木 大輔)
申し訳ありませんが、6月中のブログは、都合により休ませていただきます。
次回のブログは、7月11日を予定しております。