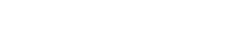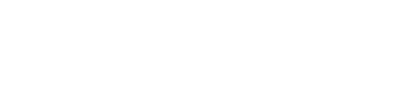ビリー・ホリデイを聴く
―いけないケムリと水で その身をけずり落としてまでも―
(星空のビリー・ホリデイ)
読書をしながら何か音楽を聴きたくて、いろいろCDをかけていたところ、最後にかけたビリー・ホリデイ(アメリカのジャズ歌手)が読みかけの小説の雰囲気に妙にはまり、はからずも久しぶりに彼女の歌を聴くことになりました。
彼女の声が持つ圧倒的な存在感は、本質的にはBGMになり得ないものですが、小説の雰囲気がとても軽やかだったため、彼女の歌とぶつかることなく、読み進めることができたのかもしれません。
本を読み終え、今度は彼女の晩年の名盤『Lady in Satin』と『BillieHoliday(ラスト・レコーディング)』を聴きました。
『Lady in Satin』の冒頭、スピーカーから飛び出すしわがれ声には、分かっていても一瞬たじろぎます。衰えは著しく、音程も不安定、技術的に言えば断じて上手い歌ではありません。
後年、若い頃の瑞々しい歌声を失ったのは、麻薬とアルコールに溺れた彼女の自業自得とはいえ、思い通りに歌えない彼女の苦しみと悲しみが伝わってきて、息が苦しくなるほどです。
一方、『Billie Holiday』における彼女は、晩年にしては声もよく出ており、曲が進むにつれ、声に歌う喜びが乗ってきます。バックを務めるミュージシャンも、彼女の希望をかなえたメンバーが揃いました。
彼女の白鳥の歌となった、アルバムの最後を飾る曲「Baby Won’tYou Please Come Home」は、苦悩に満ちた人生の締めくくりとしては意外なほど、明るさに満ちています。
―so long 黄昏を歌に秘めたら―(星空のビリー・ホリデイ)
初めて彼女の歌を聴いたのは、ちょっと背伸びをしたかった中学生の時。大人の世界を覗いたような気分になりましたが、結局、その時は良さを理解できませんでした。
しかし、年齢を重ねるにつれ、少しずつ彼女の魅力(というよりも、彼女の引き受けた孤独とは何たるか)を分かり始めたような・・・
でも、正直なところ、やっぱり分からない。
村上春樹氏は著書の中で、彼女の歌を「癒し」ではなく「赦し」と表現しましたが、その感覚も私には分からない。
それは、まだ、なのか。
それとも、ずっと、なのか。
今朝のお供、
サザンオールスターズの曲「星空のビリー・ホリデイ」。
(佐々木 大輔)