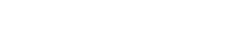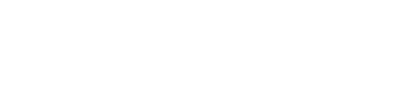真実を見抜く目を養う
先日、堤未果著『政府は必ず嘘をつく』という本を読みました。
あまり品がいいとは言えないタイトルですが(最近はインパクトばかりを重視したタイトルの本が多く、あまり感心しません)、その内容は、9.11同時多発テロ以降のアメリカが抱える問題を明らかにし、東日本大震災以降の日本が同じ轍を踏まないよう警告するものでした。
堤氏は、ベストセラーとなった『ルポ 貧困大国アメリカ』等の著作でも知られるジャーナリストです。
本書でまず目を引いたのは、「コーポラティズム」という言葉。
堤氏によると、想像を絶する資金力をつけた経済界が政治と癒着することを表す言葉とのことです。
堤氏は、アメリカの現状について、レーガン政権がメディアの企業所有を解禁して以来、大資本によるマスメディア(テレビや新聞等)の集中と系列化が進んだことで、情報操作が頻繁に起こるようになり、多様な意見が反映されなくなっていることを指摘。その結果、アメリカの政治は、資本が裏で糸を引く、名ばかり二大政党と化し、「資本独裁国家」とでも呼ぶべき状態に陥っていると慨嘆します。
これはアメリカに限られたことではないでしょう。
では、どうすれば真実を見抜くことができるのか。
堤氏は、「腑に落ちないニュースがあったら資金の流れをチェック」し、「情報を比較する」ことが大切であると説きます。
その具体例のひとつとして挙げられているのが、2011年にリビアで起こった民主革命です。
民主革命である「アラブの春」が、リビアにも拡大したことを喜ぶリビア国民の様子が、日本においても連日報道されました。
しかし、堤氏は、「カダフィ政権が、ドルとユーロに対抗するための統一通貨ディナの導入を計画していたこと」こそが、リビアの民主革命の引き金であったと看破し、「ディナが実現すれば、アラブとアフリカは統合され、石油取引の決済がドルからディナに代われば、基軸通貨であるドルの大暴落は避けられない」とするアメリカの憂慮が、リビア国民の民主化機運の高まり以上に、色濃く反映されたものであったと主張します。
ちなみに、「アラブの春」の立役者となったフェイスブック(インターネット上において、同じ目的を持つ仲間が交流を図るための会員制サービス)は、アメリカの会社が提供するサービスです。
ただし、本書の内容を全て鵜呑みにするのはいかがなものかな、というのが私の正直な感想です。
本書には、たとえば立憲主義に対する堤氏の誤認(直接本書のテーマとは関係がない部分であり、揚げ足をとるつもりはありませんが)などがあり、はたして全ての内容が正しい知識に基づいて書かれているのか心許なく思うところもあります。
また、堤氏の主張を裏付ける証言が、特定の人物からのみ得られたものであることが多く、公平さという側面にも疑問が残ります。
本書の内容も、堤氏というひとりのジャーナリストが発するひとつの情報ですから、堤氏自身が指摘するように、他の情報と比較し、多角的な視点で考察する必要があるでしょう。
本当のメディアリテラシー(テレビや新聞等からの情報を主体的・批判的に読み解く力)が試される一冊なのかもしれません。
今朝のお供、
MEGADETH(アメリカのバンド)の『RUST IN PEACE』。
サマソニのセットリストがコンパクトながらも豪華で・・・
(佐々木 大輔)