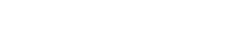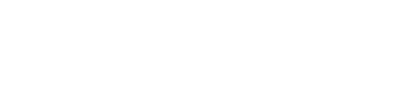今年もよろしくお願いいたします。
昨年はベートーヴェン生誕250周年のアニバーサリーイヤー。年末には日本中でベートーヴェンの交響曲第9番『合唱付き』(第九)が鳴り響くはずでした。しかし結果は・・・。
たしかに、第九の演奏にかかるオーケストラは大編成ですし合唱もあるのですから、このご時世に最も不向きな楽曲といえるでしょう。
ところで、我が国において“年末といえば第九”が恒例になったのは、諸説ありますが、音楽関係者が年を越す餅代を稼げるようにするため(つまりは、オーケストラの団員、合唱団のメンバーの知人友人が聴きに来るので、チケットが捌けるから)と言われています。
事の真相はともあれ、年末恒例行事となっていることは間違いなく、第九が流れ始めると1年の終わりを感じるものです。
一方でヨーロッパに目を向けると、第九は年末恒例というわけではなく、特別な機会に演奏される楽曲とされているようです(今でも年末に第九演奏を慣習としているのは、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団くらいでしょうか)。
まず思いつくのは、第2次世界大戦後に再開された最初のバイロイト音楽祭(1951年)でフルトヴェングラーが指揮した第九。これは、第九史上最高の名演と語り継がれておりますし、そもそも第九は、ワーグナーが自身の楽劇(オペラ)を上演するためだけに創設したバイロイト音楽祭で、唯一演奏されるワーグナー以外の楽曲なのです。ベートーヴェンを崇拝するワーグナー自身がバイロイト祝祭劇場の定礎記念で演奏したことから、別格扱いとなっています。
また、ベルリンの壁崩壊を祝ってバーンスタインが指揮した第九(1989年)は、バイエルン放送交響楽団を中心に東西ドイツ並びにアメリカ及びソ連等連合国側をそれぞれ代表するオーケストラから団員が参加した特別オーケストラとともに演奏されました。そして何より、第4楽章の合唱で歌われるシラーの『歓喜に寄す』の歌詞を、「歓喜(フロイデ)」から「自由(フライハイト)」へと歌い替えたことでも話題になりました。一部では「けしからん!」との声もあったようですが、バーンスタインの演奏が説得的であったこと、自由を勝ち得た喜びから、ベートーヴェンも草葉の陰で納得し、“おふくろさん騒動”にならずに済んだのかもしれません。
生演奏で聴く第九の素晴らしさは何にも代えがたいものですが、もうしばらくはCDやレコードの録音で我慢。
いつか心置きなく生演奏で音楽を聴ける日々が戻ったら、私は真っ先に第九を聴きたい。
叶うなら、1770年12月生まれのベートーヴェンが満251歳の誕生日を迎える前に。
今朝のお供、
Pearl Jam(アメリカのバンド)のアルバム『Ten』。
(佐々木 大輔)
自室のCD・レコード棚を眺めると、ベートーヴェンの交響曲全集(全9曲)が15組。これを多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれかと思いますが、何組買ってもどのセットを買っても収録されている交響曲は同じ9曲であり、10曲にもならなければ8曲でもありません(そもそも8曲収録では全集と呼ばれません)。
それではなぜ同じ曲のCDやレコードを何枚も買ってしまうのか。
答えの前にちょっと寄り道をお許しください。
私が幼い頃、わが家ではいつも音楽がかかっていましたが、その多くはベートーヴェンでした。
幼い頃からクラシック音楽を聴いて育った私は、中・高校生になると変に背伸びをして、『運命』交響曲や『田園』交響曲といった有名どころはもう卒業とばかりに、あまり有名ではない曲を聴いて「周りとは違う」アピールをしていたように思います。ところが、そのようなマニアックな曲というのはとっつきにくく(だからなかなか人気曲にならないのですが)、ある程度の経験がないと良さどころか聴き方すら分からないという難物なんですね。有名曲には戻りたくないけれどマニアックな曲には跳ね返されて前に進めない。私は袋小路にはまってしまいました。
さて、クラシック音楽とどのようにお付き合いすればよいものか・・・
結局、当時所属していたオーケストラが演奏会で演奏する曲の予習としてCDを購入し、受動的に聞いているだけの日々。
そうこうしているうちにオーケストラを卒業し、聴く専門となってしまった10代の終わり、またしてもクラシック音楽とのお付き合い問題が再燃することに。その時たまたま手にしたのが、某評論家による指南書でした。
まずは知っている曲の評論を読もうと、最初に開いたのがベートーヴェンの交響曲第5番『運命』のページ。推薦されていたのはフルトヴェングラー指揮とカルロス・クライバー指揮のCDでした(これらは万人が認める20世紀の名演奏です)。
フルトヴェングラーの方は1947年5月、ベルリン・フィルの指揮台に復帰した記念コンサートのライヴ録音。音は古く録音もモノラルですが、「苦悩から歓喜へ」という「運命のドラマ」そのままに熱狂的な演奏で、すぐに大好きになりました。
一方のクライバー。ともすれば通俗的に堕しがちな「運命のドラマ」はここにはなく、ひたすら純粋にベートーヴェンが作曲した「5番目の交響曲」が演奏されています。金管の強奏、リズムの弾みを聴くたびに、ベートーヴェンはかくも爽快で瑞々しい音楽を書いたのかと、「運命のドラマ」に覆い隠されて見えなくなっていた音楽そのものの鮮度に驚きます。
ちなみに、交響曲第5番を『運命』と呼ぶのは日本くらいで、世界的にはこのニックネームは使われておりません。輸入盤のCDジャケットを見ても「Symphony No.5」などと印字されているのみで、『運命』に当たる単語は記載されておりません。
このように、同じ『運命』でも演奏家が違うとこんなにも違って聞こえるんだなあと思ったのがきっかけとなり、私とクラシック音楽との新しいお付き合いが始まりました。
すなわち「好きな曲ができたらいろいろな演奏で聴く」。
このような聴き方をすることによって曲に対する理解は深まり、多くの演奏家の特徴を知ることもできます。
また、有名曲は卒業したなどと恥ずかしいことは言わずに、どんな曲にもまっさらな気持ちで向き合ってみようと心を新たにするきっかけにもなりました。
幼い頃、音楽を聴く「耳」を育ててくれたベートーヴェン。そして、今に至る音楽との付き合い方を教えてくれたベートーヴェン。
今年は‘恩師’ベートーヴェンの生誕250周年。
今の私は晩年の作品に強く惹かれます。10代の頃に馴染めなかった作品です。
当時はきっとベートーヴェンに見透かされていたのでしょう。そんなに背伸びをしたって駄目だよ、と。
今は少しだけベートーヴェンも私のことを受け入れてくれたと思いたいな。
今朝のお供、
サザンオールスターズの『ステレオ太陽族』。
デビュー記念日に有料配信された無観客ライヴ。「朝方ムーンライト」が聴けて嬉しかった。
(佐々木 大輔)
今年は5年に1度のショパン国際ピアノ・コンクール(ショパン・コンクール)の年。
ショパン・コンクールは世界最高峰のコンクールのひとつとして広く知られています。
過去には、マウリツィオ・ポリーニ(第6回1960年)、マルタ・アルゲリッチ(第7回1965年)、クリスティアン・ツィメルマン(第9回1975年)といった錚々たるピアニストが優勝しています。また、1985年に優勝したブーニンの日本における熱狂的な人気ぶりをご記憶の方も多いのではないでしょうか。
ショパン・コンクールは予選からファイナルまで、一貫してショパンの楽曲のみを演奏します。そこで、(技術的に少々難があっても)魅力的なショパンを演奏するピアニストを評価するのかそれとも総合的にみてハイレベルなピアニストを評価するのかということが問題となり、ショパンの解釈については「ロマンティック派」を推すのか「楽譜に忠実派」を推すのかということが問題になります。
「正しい演奏とは何か」とは永遠の課題であり、青柳いづみこ氏の著書によると、それは多分に政治的な駆け引きの中で揺れ動き、若き才能を発掘するはずが、審査員同士の争いに化けてしまうこともしばしばというちょっと嫌な現実も。
そもそも“芸術”に点数をつけること自体に無理があると言えばそれまでかもしれませんが。
ところでショパン・コンクールは、開始当初から是が非でもショパンの祖国ポーランドから優勝者を輩出したいという思惑がありながら、第1回大会ではソ連のピアニスト(レフ・オボーリン)が優勝するという幕開けでした。それは、冷戦真っただ中のソ連が、国の文化的威信をかけて開催したチャイコフスキー国際コンクールの第1回大会(1958年)ピアノ部門において、アメリカ人であるヴァン・クライバーンが優勝したのと似たようなものでしょうか。
その後ショパン・コンクールは、ソ連とポーランドのピアニストの優勝が続き、第6回大会で初めて西側(イタリア)のピアニストであるポリーニが優勝したという経緯があります。
どうしても政治的な色を帯びてしまうのは、国レベルでもそれだけ重要なコンクールであることの表れとは思いますが、審査の裏側を覗いてしまうと、純粋にコンクールを見ることができなくなってしまうのは悲しいものです。
それでも私は、私情も政治もねじ伏せるだけの圧倒的な才能の出現を毎回期待しています。
そしてコンテスタントの皆さんには、結果に一喜一憂することなく、自分の才能を信じて、将来にわたり素晴らしい演奏を聴かせてもらいたいと願っています。
今朝のお供、
マウリツィオ・ポリーニの演奏によるショパンの『練習曲集』。
(佐々木 大輔)