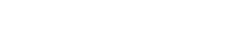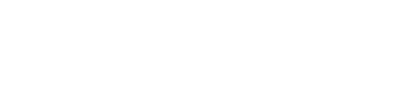―村上春樹とは、読む度、好きと思ったり嫌いと思ったり、アンビバレント(愛憎こもごも)な感情を抱く存在である―
今年2月に発表された村上氏の『騎士団長殺し』を読む準備運動として、村上氏の初期作品『風の歌を聴け』、『1973年のピンボール』、『羊をめぐる冒険』(以上、青春三部作)を再読しました。村上氏の作品は、大学生の頃に初めて読んで以来、折に触れて読み返しています。
今回の再読で最も考えさせられたのは、青春三部作の中では人気も世評も控えめな『ピンボール』。「僕」と双子の姉妹との日常、そしてデビュー作『風の歌』から続く「鼠」との友情を描いた作品です。双子の姉妹がどこからかやってきて、どこかへといなくなってしまったように、「僕」は物事に執着することなく、ただ事実を受け流します。一方、「鼠」は街を出ていくことを決意します。
「鼠」は「僕」の分身であり、社会にコミットメント(関与)出来ないでいる「僕」が生み出した「僕のあるべき姿」ではないか、と私は考えます。
一般的に村上作品の登場人物は、物事にかかわりをもたず無関心であること(デタッチメント)を特徴とし、それが人間関係や社会に縛られたくないと思っている人々の共感を呼んでいるところもあるかと思うのですが、私が、「僕」は社会にコミット「しない」のではなく「出来ない」のだと感じるのは、本作における「鼠」の決断に至る葛藤が、失うことを恐れて決断出来ない「僕」の葛藤として映るからです。「僕」自身、変わらなければならないことを分かっているんじゃないのかな。
実際、村上作品は、『ねじまき鳥クロニクル』で「デタッチメントからコミットメントへの転換」があり、その姿勢は、地下鉄サリン事件を扱ったノンフィクション『アンダーグラウンド』、阪神大震災を契機とした連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』に顕著です。
このような過去の作品とのつながりも考えながら、いよいよ最新作『騎士団長殺し』に突入。
果たして村上氏が本作で紡いだ物語は魅力的であったでしょうか。
残念ながら私は楽しめませんでした。それゆえ「私の好まない村上春樹」ばかりが目に付いてしまったようです。
謎の美少女、(井戸のような)穴と壁、都合のいい女性、お酒と料理と音楽・・・いつものレギュラーメンバー。
私の方が「やれやれ」と言いたい。
これらの「メタファー」を読み解くことが村上作品を読む楽しみであることは理解できます。しかし、その謎解きを楽しめるほど夢中になれなくなったのは、私が社会にコミットする立場にあり、(デタッチメントを脱したとはいえ)社会性の乏しい登場人物らに共感できなくなってしまったからかもしれません。
とはいえ、以上はあくまでも「物語」についての感想。
本作を通じて村上氏は何を語りたかったのか。
これについては私なりに感じるところがあり、深く考えさせられたことも事実。だからこそ、冒頭のアンビバレントな感情を抱きつつ、村上氏の作品から目が離せないのです。
今朝のお供、
ショルティ指揮ウィーン・フィルの演奏によるR.シュトラウスのオペラ『ばらの騎士』。
(佐々木 大輔)
先日、第156回直木賞の発表がありました。
受賞作は恩田陸著『蜜蜂と遠雷』。
新刊をあまり読む機会のなくなった私が、学生時代にお世話になったカフェのマスターから薦められて、昨年久しぶりに手にした新刊書でした。
ピアノコンクールに挑む若きピアニストたちの群像劇。これから読まれる方もたくさんいらっしゃるでしょうから、あまり内容には触れないようにしますが、演奏者によって解き放たれる音の一粒一粒が、目に見えるかのように描写されていきます。音楽を紡ぐ著者の言葉。それは、私の中に記憶として残る過去の名演奏を想起させるのではなく、今まさに目の前で生み出された未知の音を聴かせてくれるのです。
恩田氏は本作において、音楽を解説することではなく、「言葉で音楽を奏でること」に挑んだのではないでしょうか。
読了後、小説の中で採りあげられた数々の名曲たち(幸いにも音源が手元にあったので)を聴きながら余韻に浸りつつ、音楽を聴く際は、もっとしっかり音楽と向き合って聴かなければいけないなと、“ながら聴き”に堕しがちな自分を戒める機会にもなりました。
『蜜蜂と遠雷』で恩田氏の小説に初めて触れ、直後にもう1冊読んだのが『夜のピクニック』です。
以前から本屋に行くたび気になっていた小説で、著者名とタイトルだけは知っていました。
なかなか手が伸びなかったのは、この小説につけられた「永遠普遍の青春小説」というキャッチコピーのため。そろそろ不惑なもので、今さら青春小説と言われてもなあ・・・と気おくれを感じていたのです。
―全校生徒が夜を徹して80キロを歩きとおす北高の伝統行事「歩行祭」。甲田貴子は密かな決意を胸に抱き、「歩行祭」に臨む。高校生活最後のイベント。果たして彼女の思いは実を結ぶのか―
舞台は「歩行祭」ゆえにひたすら歩くだけ。特別な事件は起こりませんが、登場人物たちの心の機微を通じて、私にも確かにあった遠い過去に再会することができました。
「もっと、ちゃんと高校生やっとくんだったな」。
読み終えてからネットの読者レビューなどに目を通すと、私と同じセリフに共感した人がけっこういました。「みんなそういう思いを抱えて年齢を重ね、今を生きているのだな」と仲間意識が芽生え、一緒にお酒でも酌み交わしたい気持ちになったのはご愛嬌、ということで。
今朝のお供、
Carpentersの曲「I Need to Be in Love(青春の輝き)」。
(佐々木 大輔)
「良い文章を書くには、たくさん本を読んでください」
先日、日本ペンクラブ副会長西木正明先生と会食させていただく機会がありました。
西木先生のことは皆さんご存知かと思いますが、「凍れる瞳」「端島の女」で直木賞を受賞された秋田県仙北市出身(旧仙北郡西木村)の作家です。
私を誘ってくださった方の話によると、先生は、会食当日も選考委員を務めている「さきがけ文学賞」の授与式に参加されるなどご多忙を極める中、特別に時間をとってくださったとのことでした。
冒頭の言葉は、程良く場が温まった頃合い、同席した方からの質問に答えて先生がおっしゃった言葉です。
お会いした先生の印象は、物腰が柔らかく色気のある紳士。どんな質問にも丁寧に、かつユーモアと少しの毒を交えて答えてくださいました。アメリカ大統領選挙から音楽における同曲異演まで話題は多岐にわたり、私など文壇の裏話には思わず身を乗り出してしまう始末。
ちなみに、音楽家で最近のお気に入りはグスターボ・ドゥダメル(ベネズエラ出身の若手指揮者)とのことですから、先生は私よりもはるかに感性がお若い!
会食させていただくに当たり、いくつか先生の著書を読み返しました。その中のひとつが『極楽谷に死す』という短編集です。
先生と思しき主人公が、70年代初頭を共に過ごした友人たちとの再会をきっかけに遠い記憶を呼び起こしていくという作品集で、思い出の過去として描かれる70年代は熱気に満ちているのですが、どこか刹那的な衝動に支配されているむなしさを感じます。いや、むしろ、刹那的だからこその熱気だったというべきでしょうか。
そう感じるのは、私が当時を生きておらず、結果を知った上で70年代の不穏な熱気を振り返るからかもしれません。
「みんな、どこにいってしまったのだろう。」
本書を締めくくる一文にも、懐かしさと背中合わせのむなしさがにじんでいるように思われます。
手持ちの著書の中から『極楽谷に死す』を含め何冊か持参したところ、快くサインに応じてくださいました。
頂いたサインを眺めるたび、先生の冒頭の言葉を思い出し、「読書という趣味を仕事にも活かしなさい」と背中を押される気持ちになります。
今朝のお供、
THE YELLOW MONKEY(日本のバンド)の曲「砂の塔」。
カップリングには再終結後のアリーナツアーのライヴ音源12曲を収録。15年振りのライヴの1曲目を飾った「プライマル。」、清々しさと未練が刻まれた思い出からの卒業。 準備 ALRIGHT!
(佐々木 大輔)