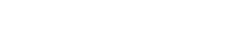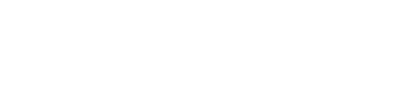最近、マーク・ロスコの画集を手に取ることが多くなりました。
ロスコは、生前、もっぱら人間の基本的な感情(悲劇、忘我、運命)を表現することに関心を寄せ、自分が絵を描くことは「自己表現ではなく他人に向けたコミュニケーションである」と定義していました。鑑賞者とのコミュニケーションを作品の根幹におくことから、鑑賞者の内面を映す鏡のような作品と評されることもあるようです。
ロスコの作品には、タイトルがついていないもの(『無題』と題されたもの)が多いため、「何が描かれている作品か」ということを推測する手掛かりがありません。一方で、タイトルが無いことは、作品の見方を限定されずに鑑賞できるという利点もあります。
海外では、悲劇性が強調されて受けとめられることもあるとのことですが、私の場合、ロスコの作品を観ることで、意識が自己の内なる深淵へとゆっくりと導かれ、自分を見つめ直すきっかけとなり、その結果、様々な物事や感情が整理されて心が穏やかになっていくことに魅力を感じます。
ある本には、「多くの人は、ロスコの作品を右脳で鑑賞しているようだ」と書かれていました。
言語や論理をつかさどる左脳と、感覚や感情をつかさどる右脳。
とすれば、ロスコの作品は、日々文章と向き合う仕事をしている私にとって、理屈から感性へ、仕事脳からプライベート脳へ、スイッチを切り替えてくれる効果があるのかもしれません。
千葉県佐倉市にある川村記念美術館には、ロスコの『シーグラム壁画』と呼ばれている作品群のうち、7点が収蔵されています。
『シーグラム壁画』は、もともと、「最高の料理と現代アートをともに提供する」というコンセプトで創設されたレストランから、ロスコが一室の装飾を依頼されて作成したものでした。
ところが、レストランの雰囲気に幻滅したロスコが、契約を破棄してしまったため、これらの作品群は一旦お蔵入りとなってしまいます。
その後、9点がロンドンのテイト・ギャラリー(テイト・モダン)に寄贈され、1990年には川村記念美術館が7点を購入したことにより、これらの作品群を鑑賞することができるようになりました(残りはワシントンDCのナショナル・ギャラリーなどが所蔵)。
テイト・モダンと川村記念美術館では、これらの作品群のために、ロスコが望んだとおり、ロスコの作品のみを展示した一室を設けています。
ロスコ作品のみが飾られた空間を持つ美術館は、上記の美術館をあわせても、世界でたった4つだけです。
いつかこれらの美術館を巡る旅をしてみたいものです。
※本文の情報は、私の所有している海外版の画集や書籍から得たものであり、もしも誤りがあるとすれば、その全ては私のつたない語学力に起因するものであることをお許しください。
今朝のお供、
SEKAI NO OWARI(日本のバンド)の『Tree』。
久しぶりに現れたヒットチャートを駆け抜ける若いバンドにワクワクしています。
青さも感じるけれど、求める音に対してはもっと尖っていけばいい。
(佐々木 大輔)
先日、秋田県立近代美術館に『大原美術館展』を観に行ってきました。倉敷市にある大原美術館にはなかなか行く機会が無く、大原美術館所蔵の作品を観るのは、宮城県美術館に『大原美術館展』を観に行って以来9年振りです。
今回の『大原美術館展』、エル・グレコの「受胎告知」やカンディンスキーの「先端」が貸し出されていなかったのは残念でしたが(特にカンディンスキーは、観られるものと思って行ったものですから・・・)、珠玉の作品、セガンティーニの「アルプスの真昼」を観ることができました。
雲ひとつなく晴れ渡った空の鮮やかな青。広がる草原は、降り注ぐアルプスの陽光に輝いています。
遠くに見える山脈。
白い山羊と白樺の枝。
画面中央で(白樺に身を預けて)休む女性。
観れば観るほど完璧な構図です。
絵に近づいて観ると、草の一葉ごとに絵具が置かれており、一葉一葉独立して光を映していますが、少し離れると、色が混じり合い調和されて、草原全体で眩い光を放ちます。
実は、前回仙台で観た時はあまり魅力を感じなかった「アルプスの真昼」。はたして、9年前はそれほど心を動かされなかった絵に、なぜこうも惹かれるようになったのか。
前回鑑賞した時は、漠然としたものでしたが、あふれる光の裏にどことなく漂う「陰り」を感じたのです。
闇がある、とまでは言い過ぎかもしれませんが、光は潜在的に影の存在を意識させるものです。
この「陰り」に少しずつ心を捉われていった9年間。
調べてみると、彼の画風は、暗い色調の初期から、分割主義という技法(パレット上で色を混ぜ合わせないで、一筆一筆を細かくぬりかさねて描くという技法)を用いた明るい色調の中期、そして象徴主義の代表的な画家となった後期へと変わっていったとのことです。初期の暗い色調の画風には、彼自身の生い立ちが影響しているとする説もあります。
「アルプスの真昼」は中期の作品です―セガンティーニには、同時期に描いた同じタイトルの姉妹作があり、そちらの絵はセガンティーニ美術館(スイス)に所蔵されています―
彼は、暗い影を振り払い、光の画家へとすっかり変化することができたのか。それとも、画風はいかに変化しようと、どこまでも暗い影をまとい続けたのか。
今回の美術展で鑑賞した感想から、私は後者のような気がしてなりません。
もちろん、これは、多分に個人的なセンチメンタリズムに起因するものであり、全くもって確証があるものではないのですが。
今朝のお供、
アデル(イギリスのミュージシャン)の『19』。
(佐々木 大輔)
去る9月28日、秋田県立美術館(新県立美術館)が本オープンしました。
一番の注目は、5枚の絵から成る藤田嗣治の大壁画『秋田の行事』。
8月31日の早朝、平野政吉美術館からの搬出入が細心の注意をもって行われ、移設は無事に完了しました。
私は『秋田の行事』が大好きで、県外に住んでいた頃も、帰省すると平野政吉美術館へ観に行きました。平野政吉美術館は建築としても味わいがあり、絵を観るだけではなく、訪れることにも楽しみがありましたので、この度の移設には一抹の寂しさを覚えます。
しかし、新県立美術館を設計した安藤忠雄氏は、平野政吉美術館の特徴ある屋根と丸窓が、館内のカフェから見えるように設計しており、平野政吉美術館も秋田が誇る芸術作品として尊重されています。
「世界一巨大な絵を、誰にもできないような速さで仕上げて見せましょう」。
平野政吉から依頼を受けた藤田はこのように答え、『秋田の行事』の製作に着手しました。普段は絵を描く姿を他人に見せない藤田が、この時ばかりは押しかける見物人を一向に気にすることなく、ときには見物人に竿灯を上げるポーズをとらせるなど、むしろ注目されることを楽しんでいたようだとの証言も残されています。
米蔵を改造したアトリエで、秋田民謡を絶え間なく流しながら、下書きもせず一気呵成に描き上げ、最後に「一九三七 昭和十二年自二月二十一日 至三月七日 百七十四時間完成」と記して絵筆を擱きました。藤田も壁画の完成に興奮したのでしょう、飲めないお酒をおちょこで2杯飲んだとの記録もあります。
しかし、『秋田の行事』は、大戦の影響を受け、完成後30年もの間平野家の米蔵で眠ったままとなり、ようやく公開されたのは、平野政吉美術館が完成した1967年(昭和42年)、藤田の亡くなる前年のことでした。
もちろん、私は『秋田の行事』だけではなく、他の藤田作品も大好きです。2006年に生誕120年を記念して、東京国立近代美術館で開かれた世界最大規模の藤田嗣治展を、雨の中2時間待ちで鑑賞したことも思い出です。
藤田の描く女性は、表情の乏しさがかえって陶器のような美しさを印象付けますが、晩年の代表作『カフェ』に描かれた頬杖をつく女性は、珍しく憂いを湛えた表情を持ち、蠱惑的な色気に満ちていて、絵の前から動けなくなるほどでした。
日本画壇との軋轢により、大戦が終わるとフランスに戻り(のちに帰化)、再び日本の地を踏むことはなかった藤田ですが、彼の作品が秋田に多数残されていることは、我が故郷の誇りです。
今朝のお供、
My Bloody Balentine(アイルランドのバンド)の『Loveless』。
(佐々木 大輔)