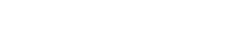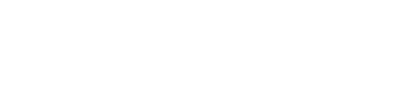先ごろ読んだ小説の影響で、すっかりアンリ・ルソーに夢中になってしまいました。
ルソーの画家デビューは49歳と遅く、それ以前は税関に勤務しながら絵を描いていました。そのため、いわゆるアカデミックな教育を受けておらず、遠近法などの絵画技術を身に着けていなかったようです。
技術的に稚拙と言われる彼の作品は、当時の評論家から酷評され、無審査で応募者全員の作品が展示された展覧会では、新聞等での酷評を知った人々が作品の前に群れをなし、銘々お腹を抱えて大笑い、中には呼吸困難に陥った人もいたそうです。
しかし、晩年には、ルソーを評価する評論家や画家仲間も現れ、特にピカソに影響を与えたというエピソードは、間接的にルソーの評価を高める契機となりました。
とはいえ、未だ「日曜画家」「(画家ではなく)税関吏ルソー」などと揶揄されることも多く、その評価が定まっているとはいえません。
先に挙げた小説には、ルソー(と彼に関わった人々)のエピソードがふんだんに盛り込まれていて、ルソーを好きな方にはお馴染みの話でも、浅学な私にとっては初耳の話も多く、人間ルソーを知るきっかけとなりました。
ルソーの作品といえば、私にとって、『蛇使いの女』、『詩人に霊感を与えるミューズ』、『夢』など、ジャングルを描いた絵のイメージが強く、これらの作品を、「あの葉陰には見たこともないような気味の悪い生き物が潜んでいるのではないか」、「そんなじめじめとした茂みの中に、裸で体を横たえることに抵抗はないのだろうか」などとつまらぬ想像や心配をしながら、どこか怖いものみたさで鑑賞しているところがありました。
改めて作品を見てみると、ルソーは大好きな自然を克明に描くため、多種多様な緑色(作品によっては21種類も使用しているとのこと!)を使い分けており、その執念にも似た凄みが作品から伝わってきます。
もっとも、神秘的でグロテスクな作品という印象は変わらないけれど。
―情熱がある。画家の情熱のすべてが―
(原田マハ著『楽園のカンヴァス』)
登場人物が発したこの言葉のとおり、小説を読んでいる間、ルソーが絵にかけた情熱、その作品を心から愛する人々の情熱にほだされて、ルソーと時代を共にしたような、夢を見ているように幸せな時間を過ごすことができました。
夢から覚めた今は、時間ができると、手持ちの画集やインターネットからルソーの絵を探し出し、“夢をみた”余韻に浸っています。
今朝のお供、
Blur(イギリスのバンド)の『The Magic Whip』。
(佐々木 大輔)
最近、マーク・ロスコの画集を手に取ることが多くなりました。
ロスコは、生前、もっぱら人間の基本的な感情(悲劇、忘我、運命)を表現することに関心を寄せ、自分が絵を描くことは「自己表現ではなく他人に向けたコミュニケーションである」と定義していました。鑑賞者とのコミュニケーションを作品の根幹におくことから、鑑賞者の内面を映す鏡のような作品と評されることもあるようです。
ロスコの作品には、タイトルがついていないもの(『無題』と題されたもの)が多いため、「何が描かれている作品か」ということを推測する手掛かりがありません。一方で、タイトルが無いことは、作品の見方を限定されずに鑑賞できるという利点もあります。
海外では、悲劇性が強調されて受けとめられることもあるとのことですが、私の場合、ロスコの作品を観ることで、意識が自己の内なる深淵へとゆっくりと導かれ、自分を見つめ直すきっかけとなり、その結果、様々な物事や感情が整理されて心が穏やかになっていくことに魅力を感じます。
ある本には、「多くの人は、ロスコの作品を右脳で鑑賞しているようだ」と書かれていました。
言語や論理をつかさどる左脳と、感覚や感情をつかさどる右脳。
とすれば、ロスコの作品は、日々文章と向き合う仕事をしている私にとって、理屈から感性へ、仕事脳からプライベート脳へ、スイッチを切り替えてくれる効果があるのかもしれません。
千葉県佐倉市にある川村記念美術館には、ロスコの『シーグラム壁画』と呼ばれている作品群のうち、7点が収蔵されています。
『シーグラム壁画』は、もともと、「最高の料理と現代アートをともに提供する」というコンセプトで創設されたレストランから、ロスコが一室の装飾を依頼されて作成したものでした。
ところが、レストランの雰囲気に幻滅したロスコが、契約を破棄してしまったため、これらの作品群は一旦お蔵入りとなってしまいます。
その後、9点がロンドンのテイト・ギャラリー(テイト・モダン)に寄贈され、1990年には川村記念美術館が7点を購入したことにより、これらの作品群を鑑賞することができるようになりました(残りはワシントンDCのナショナル・ギャラリーなどが所蔵)。
テイト・モダンと川村記念美術館では、これらの作品群のために、ロスコが望んだとおり、ロスコの作品のみを展示した一室を設けています。
ロスコ作品のみが飾られた空間を持つ美術館は、上記の美術館をあわせても、世界でたった4つだけです。
いつかこれらの美術館を巡る旅をしてみたいものです。
※本文の情報は、私の所有している海外版の画集や書籍から得たものであり、もしも誤りがあるとすれば、その全ては私のつたない語学力に起因するものであることをお許しください。
今朝のお供、
SEKAI NO OWARI(日本のバンド)の『Tree』。
久しぶりに現れたヒットチャートを駆け抜ける若いバンドにワクワクしています。
青さも感じるけれど、求める音に対してはもっと尖っていけばいい。
(佐々木 大輔)
先日、秋田県立近代美術館に『大原美術館展』を観に行ってきました。倉敷市にある大原美術館にはなかなか行く機会が無く、大原美術館所蔵の作品を観るのは、宮城県美術館に『大原美術館展』を観に行って以来9年振りです。
今回の『大原美術館展』、エル・グレコの「受胎告知」やカンディンスキーの「先端」が貸し出されていなかったのは残念でしたが(特にカンディンスキーは、観られるものと思って行ったものですから・・・)、珠玉の作品、セガンティーニの「アルプスの真昼」を観ることができました。
雲ひとつなく晴れ渡った空の鮮やかな青。広がる草原は、降り注ぐアルプスの陽光に輝いています。
遠くに見える山脈。
白い山羊と白樺の枝。
画面中央で(白樺に身を預けて)休む女性。
観れば観るほど完璧な構図です。
絵に近づいて観ると、草の一葉ごとに絵具が置かれており、一葉一葉独立して光を映していますが、少し離れると、色が混じり合い調和されて、草原全体で眩い光を放ちます。
実は、前回仙台で観た時はあまり魅力を感じなかった「アルプスの真昼」。はたして、9年前はそれほど心を動かされなかった絵に、なぜこうも惹かれるようになったのか。
前回鑑賞した時は、漠然としたものでしたが、あふれる光の裏にどことなく漂う「陰り」を感じたのです。
闇がある、とまでは言い過ぎかもしれませんが、光は潜在的に影の存在を意識させるものです。
この「陰り」に少しずつ心を捉われていった9年間。
調べてみると、彼の画風は、暗い色調の初期から、分割主義という技法(パレット上で色を混ぜ合わせないで、一筆一筆を細かくぬりかさねて描くという技法)を用いた明るい色調の中期、そして象徴主義の代表的な画家となった後期へと変わっていったとのことです。初期の暗い色調の画風には、彼自身の生い立ちが影響しているとする説もあります。
「アルプスの真昼」は中期の作品です―セガンティーニには、同時期に描いた同じタイトルの姉妹作があり、そちらの絵はセガンティーニ美術館(スイス)に所蔵されています―
彼は、暗い影を振り払い、光の画家へとすっかり変化することができたのか。それとも、画風はいかに変化しようと、どこまでも暗い影をまとい続けたのか。
今回の美術展で鑑賞した感想から、私は後者のような気がしてなりません。
もちろん、これは、多分に個人的なセンチメンタリズムに起因するものであり、全くもって確証があるものではないのですが。
今朝のお供、
アデル(イギリスのミュージシャン)の『19』。
(佐々木 大輔)