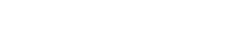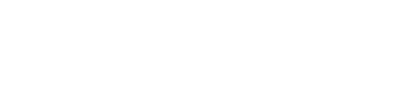アンリ・ルソーがくれた夢
先ごろ読んだ小説の影響で、すっかりアンリ・ルソーに夢中になってしまいました。
ルソーの画家デビューは49歳と遅く、それ以前は税関に勤務しながら絵を描いていました。そのため、いわゆるアカデミックな教育を受けておらず、遠近法などの絵画技術を身に着けていなかったようです。
技術的に稚拙と言われる彼の作品は、当時の評論家から酷評され、無審査で応募者全員の作品が展示された展覧会では、新聞等での酷評を知った人々が作品の前に群れをなし、銘々お腹を抱えて大笑い、中には呼吸困難に陥った人もいたそうです。
しかし、晩年には、ルソーを評価する評論家や画家仲間も現れ、特にピカソに影響を与えたというエピソードは、間接的にルソーの評価を高める契機となりました。
とはいえ、未だ「日曜画家」「(画家ではなく)税関吏ルソー」などと揶揄されることも多く、その評価が定まっているとはいえません。
先に挙げた小説には、ルソー(と彼に関わった人々)のエピソードがふんだんに盛り込まれていて、ルソーを好きな方にはお馴染みの話でも、浅学な私にとっては初耳の話も多く、人間ルソーを知るきっかけとなりました。
ルソーの作品といえば、私にとって、『蛇使いの女』、『詩人に霊感を与えるミューズ』、『夢』など、ジャングルを描いた絵のイメージが強く、これらの作品を、「あの葉陰には見たこともないような気味の悪い生き物が潜んでいるのではないか」、「そんなじめじめとした茂みの中に、裸で体を横たえることに抵抗はないのだろうか」などとつまらぬ想像や心配をしながら、どこか怖いものみたさで鑑賞しているところがありました。
改めて作品を見てみると、ルソーは大好きな自然を克明に描くため、多種多様な緑色(作品によっては21種類も使用しているとのこと!)を使い分けており、その執念にも似た凄みが作品から伝わってきます。
もっとも、神秘的でグロテスクな作品という印象は変わらないけれど。
―情熱がある。画家の情熱のすべてが―
(原田マハ著『楽園のカンヴァス』)
登場人物が発したこの言葉のとおり、小説を読んでいる間、ルソーが絵にかけた情熱、その作品を心から愛する人々の情熱にほだされて、ルソーと時代を共にしたような、夢を見ているように幸せな時間を過ごすことができました。
夢から覚めた今は、時間ができると、手持ちの画集やインターネットからルソーの絵を探し出し、“夢をみた”余韻に浸っています。
今朝のお供、
Blur(イギリスのバンド)の『The Magic Whip』。
(佐々木 大輔)