お電話でのお問い合わせ:018-864-4431
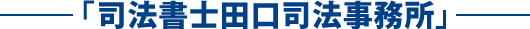

(「所有者不明の土地・建物の管理命令」、「管理不全の土地・建物の管理命令」についての当事務所の取扱業務)
① 所有者不明の「土地・建物」の管理命令申立手続(地方裁判所への申立)
② 管理不全の「土地・建物」の管理命令申立手続(地方裁判所への申立)
(目次)
1 令和5年3月31日までの財産管理制度(旧法制下)
(1) 不在者財産管理人
(2) 相続財産管理人
(3) 清算人
2 「所有者不明の土地・建物の管理制度」の創設(令和5年4月1日以降)
(1) 法改正前の問題点
(2) 法改正で変更された事項
① 管理の対象となる範囲
② 申立できる人
③ 発令のための要件
④ 管理人の仕事
⑤ 管理人の報酬
3 「管理不全の土地・建物の管理制度」の創設(令和5年4月1日以降)
(1) 法改正前の問題点
(2) 法改正で変更された事項
① 管理の対象となる財産
② 申立できる人
③ 発令のための要件
④ 管理人の仕事
⑤ 管理人の報酬
4 実務(「所有者不明土地・建物管理命令」の地方裁判所の審理等)
1 令和5年3月31日までの財産管理制度(旧法制下)
(1)旧法制下の財産管理制度の問題点
ア 原則として、財産を管理するのはその所有者自身でした。
イ 所有者以外の他人が管理するのは、例外的な場合でした。その例は、下記のとおりです。
① 不在者財産管理人
② 相続財産管理人
③ 清算人
(2)法改正で変わったこと
ア 旧法制下での問題解決のため、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う「所有者不明の土地・建物の管理制度」が創設されました。
イ 所有者が特定できない場合にも対応が可能なので、旧法制下よりも柔軟な対応を取ることができます。
ウ 共有者が不明となっているときは、不明共有持分の総体について一人の管理人を選任することが可能となりました。
(3)旧法制下の財産管理者
① 不在者財産管理人
従来の住所等を不在にしている人の財産管理をすべき者がいない場合に、家庭裁判所から選任されて、不在者の財産の管理を行う者のことです。
* (事例)
不在者財産管理人は、行方不明の人に代わって、遺産分割協議を行うことができます。
② 相続財産管理人
人が死亡して相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所から選任されて、相続財産の管理、清算を行う者のことです。
③ 清算人
法人が解散したが、清算人となる者がいない場合に、地方裁判所より選任され、法人の財産の清算を行う者のことです。
2「所有者不明の土地・建物の管理制度」の創設(令和5年4月1日以降)
(1)法改正前の問題点
法改正前の財産管理制度は、「対象となった人の財産の全てを管理する」といったように、「人単位(その人の全ての財産を管理)」で管理人を選任するというものでした。そのため、所有者が特定できない土地・建物については、旧法制下では上記のどの制度も使うことができませんでした。
(2)法改正で変更された事項
ア 概要
旧法制下での問題を解決するため特定の土地・建物のみに特化して管理を行う「所有者不明の土地・建物の管理制度」が創設されました(民法264条の2第1項、264条の8第1項)。
イ 管理の対象となる財産の範囲
管理命令の効力は、所有者不明の土地・建物のほか、下記のものに及びます。ただし、その他の財産には及びません。
① 土地にある所有者の動産
② 管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)
③ 建物の場合は、その敷地権利用権(借地権等)
* 土地・建物といっても、管理対象が厳密にそれのみに限定されるわけではないので、柔軟に対応することができます。
ウ 申立できる人
所有者不明の土地・建物の管理について利害関係を有する者が申立をすることができます。
* 利害関係人とは
利害関係の有無は、個別の事案に応じて裁判所が判断しますが、「倒壊のおそれが生じている隣地所有者」や「既に管理不全による被害受けている人」などです。
エ 発令のための要件
「所有者不明の土地・建物の管理制度」は、人の財産を所有者の許可なく扱うものですから、法律の定める要件を満たさないと発令されません。
(発令の要件)
① 調査を尽くしても、所有者又は所有者の所在を知ることができないこと。
② 管理状況等に照らして、管理人による管理の必要性があること。
* 実際には、登記簿、住民票、戸籍等を調査する必要があります。
オ 管理人の仕事
あ 対象となる財産の管理処分権は、管理人の専属となります。
い 管理人は、対象となる財産に対して、保存、利用、改良行為を行うことができます。
う 裁判所の許可を得て、対象財産を処分することができます。
え 対象財産に関する訴訟においては、管理人が当事者として、原告又は被告になります。
お 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。また、共有持分に係る管理人は、その対象となる共有者全員のために誠実公平義務を負います。
カ 管理人の報酬
あ 管理人は、対象財産から裁判所が定める額の費用の前払いや報酬を受けることになっています。つまり、費用や報酬は所有者の負担となります。
い 管理人の報酬の原資
対象財産のみではなく、基本的に、「所有者不明の土地・建物の管理人の選定」を申し立てる場合には、申立人が、予納金を裁判所へ納める必要があります。
* この予納金も、管理人の報酬の原資となります。
3「管理不全の土地・建物の管理制度」の創設(令和5年4月1日以降)
(1) 法改正前の問題点
旧法制化では、管理不全の土地・建物についての危険の回避のためには、物権的請求権等を行使して訴訟を提起し、強制執行をすることで対応していました。しかし、それでは時間が掛かり過ぎるという弱点がありました。
(2) 法改正で変更された事項
ア 概要
旧法下での不便を解消するため、管理不全の土地・建物について、裁判所が利害関係人の請求により管理人による管理を命ずる処分
を可能とする「管理不全の土地・建物の管理制度」が創設されました。
イ 管理の対象となる財産
管理命令の効力は、所有者不明の土地・建物のほか、下記のものに及びます。ただし、その他の財産には及びません。
① 土地にある所有者の動産
② 管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)
③ 建物の場合は、その敷地権利用権(借地権等)
* 土地・建物といっても、管理対象が厳密にそれのみに限定されるわけではないので、柔軟に対応することができます。
ウ 申立できる人
管理不全の土地・建物についての利害関係を有する利害関係人が申立権を有します。
* 利害関係人の例
「倒壊のおそれが生じている隣地所有者」や「既に管理不全による被害を受けている人」等です。
エ 発令のための要件
「管理不全の土地・建物の管理制度」は、本来なら、他人に管理されるはずのない財産が、第三者に管理されることになりますから、法律の定める要件をクリアしない限り、管理人選任の発令はされません。
(発令の要件)
① 所有者による土地・建物の管理が不適当であること。
② 他人の権利、法的利益が侵害されていること又はそのおそれがあること。
③ 土地・建物の管理状況に照らして、管理人による管理の必要性が認められること。
* 具体例
① ひび割れなどが生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがある場合
② 土地にゴミが大量に投棄されており、臭気や害虫による被害が生じているのに、土地所有者が放置している場合
オ 管理人の仕事
基本的には、「所有者不明の土地・建物の管理制度の管理人」と同様です。
・ただし、土地・建物の処分を行う場合、「所有者不明の土地・建物の管理制度」では、裁判所の許可だけでよかったのですが、「管理不全の土地・建物の管理制度」では、当該財産の所有者の同意も必要です。
* 管理行為の例
① ひび割れが生じている擁壁の工事を行うこと。
② ゴミの撤去、害虫の駆除
カ 管理人の報酬
対象財産たる「管理不全の土地・建物」から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受け取ることができます。
* 申立人による予納金が、管理人の報酬の原資に含まれます。
4 実務(「所有者不明の土地・建物の管理命令」の地方裁判所の審理等)
ア 裁判所では、発令に必要な法律上の要件が備わっているかを提出された資料に基づき審理しますが、審問期日を開く場合があります。
・また、申立人に追加の調査、確認を依頼する場合があります。
イ 売却や賃貸等といった、「所有者不明の土地・建物の管理命令」を発した目的が達せられたときは、原則として、申立又は職権により、裁判所は、当該命令を取り消すことになります。
ウ 区分所有建物については、「所有者不明の建物の管理制度」が適用されないため(区分所有法6条4項)、マンションなどの区分所有建物の専有部分及び共用部分について、「所有者不明の建物管理命令」を発令することはできません。
以上