お電話でのお問い合わせ:018-864-4431
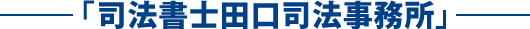

(当事務所の取扱業務)
① 「相続放棄」・「限定承認」の申立
② 相続人の捜索の公告
③ 相続財産清算人の選任
(目次)
(1) 相続人不存在(相続財産法人の成立)
(2) 相続財産法人の性格・特色
(3) 相続財産法人の管理・手続・財産の処分
① 相続財産清算人が選任されるまでの管理方法
② 相続財産清算人の選任
③ 相続財産清算人の報告
④ 相続財産法人の不成立
⑤ 相続財産清算人の代理権の消滅
⑥ 相続債権者及び受遺者に対する弁済
⑦ 相続人の捜索の公告
⑧ 権利を主張する者がない場合
⑨ 特別縁故者に対する相続財産の分与
⑩ 残余財産の国庫への帰属
⑪ 相続財産清算人の清算終了
⑫ 遺贈を受けた者の税務問題
(1) 相続人不存在(相続財産法人の成立)
ア 相続財産法人の設立(民法951条)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります。
イ 民法951条の趣旨
本条は、相続財産法人の成立要件を定めています。
(詳細)
「相続人の不存在」は、相続人の有無が不明な場合につき、下記の制度を定めていますが、本条はこの中で相続財産法人の成立要件を定めています。
① 相続人を捜索する。
一方で
② 相続財産を管理し最終的に清算する
ウ 「相続人のあることが明らかでないとき」の意義
相続開始の時を基準として、相続人の存否が不明なことをいいます。
・つまり、戸籍上、相続人が存在しない場合のことです。
・戸籍上相続人がいても、「全員が廃除」されたり、「相続放棄」して相続資格を喪失した場合も同様です。
* ① 戸籍上の相続人は存在しないが、包括受遺者がいる場合
相続財産全部ににつき包括受遺者がいるときは、相続人不存在に該当しません(最判平9・9・12)。
(理由)
包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務」を有し、相続人のあることが明らかでないときに該当しないからです(民法990条)。
・この判例は、1人への全部包括遺贈の事案ですが、包括受遺者が複数でも、財産全部が包括遺贈の対象であれば同様に解し得ます。
* 持分についての包括遺贈については、説が分かれています。
② 戸籍上の相続人は存在しないが、相続人たる身分が発生するかもしれない者がいる場合
(例) 被相続人に対して「認知訴訟」、「離婚・離縁無効確認訴訟」が継続している場合は、次の説があります。
(ⅰ) 前述の要件に該当するとして、「相続人不存在の手続」に服するとの説。
(ⅱ) 判決の確定を待つべしものとし、「その間の遺産管理は、民法918条を類推適用する」との説。
③ 次の場合は、「相続人のあることが明らかでないとき」に該当しません。
戸籍上、相続人が存在するが、その相続人が「① 所在不明」あるいは「② 生死不明」の場合
(この場合の対処仕方)
(ⅰ) 相続人の所在不明の場合
不在者の財産管理制度(民法25条以下)を準用します。
(ⅱ) 相続人の生死不明の場合
失踪宣告の制度(民法30条以下)を準用します。
(2) 相続財産法人の法的性格・特色
ア 性格
相続財産の清算を目的とする「清算法人類似の一種の財団法人的なもの」です。
(理由)
相続人不存在の場合に、主体のない財産を生じさせないために擬制されたものであるので。
イ 特色
① 外部的には、法人格を有します。
② 能力は、清算事務に限定されます。
③ 不法行為能力は、否定されています。
④ 法人なりは、格別の手続は不要です。
⑤ 法人の成立時期は、被相続人死亡の時です。
・その時に、法律上当然に法人と擬制されます。
* ただし、実際は、清算人が選任された時より、法人の存立が外形上明らかになります。
(3) 相続財産法人の管理・手続・財産の処分
第1 相続財産清算人が選任され、当該財産を引き渡すまでの管理方法
ア 「戸籍上相続人がいない場合」等で相続人がいない場合
相続財産清算人が選任されるまでは、管理ができない状態となります。
* (ⅰ) 相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判は、「利害関係人」又は「検察官」の請求によって相続財産清算人を選任しなければなりません(民法952条1項)。
(ⅱ) 家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければなりません(民法952条2項)。
イ 相続放棄によって相続人がいないことになった場合(民法940条)
相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、(相続人又は)相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。
* したがって、放棄の時に、占有していなかった者は保存義務を負いません。
第2 相続財産清算人の選任(民法952条)
ア 選任の要件
選任の要件は、下記のとおりです。
① 相続の開始
② 相続財産の存在
③ 相続人のあることが明らかでないこと。
④ 利害関係人又は検察官の請求
⑤ 選任の必要性があること。
* 成年後見人付の被相続人が死亡し、相続人は存在するが、相続人全員が判断能力(認知症等)を欠いていたり、行方不明だったりして、相続人が決まらない場合の財産管理方法
成年後見業務は終了しているので、成年後見人が相続財産を管理することはできない。そこで、相続財産を管理してもらうためには、成年後見人から家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任申立をする必要がある。
・なお、成年後見人自らを相続財産清算人としてもらうよう申し立てることも可能である。
イ 相続財産清算人の選任公告(民法952条2項)
家庭裁判所は、相続財産清算人を選任した場合、遅滞なくその旨及び相続人があるならば、一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。この場合、その期間は6か月を下ることができません。
ウ 相続財産清算人の「地位」・「権限・義務」(民法953条)
(ア) 地位
相続財産清算人は、相続財産法人の代表者とされており、相続財産に関する訴訟については、相続財産法人が当事者適格を有します。
(イ) 権限・義務
あ 民法27条の準用(清算人の職務)
相続財産清算人は、相続財産の現状を調査の上、財産目録を調整して家庭裁判所に提出する義務を負います。
い 民法28条の準用(管理人の権限)
相続財産清算人は、民法103条に定める代理人の権限の範囲内(保存行為、物・権利の性質を変更しない範囲の利用、改良行為)の権限を持ちます。
* これを超過する行為については、家庭裁判所の許可が必要です。
う 民法29条の準用(清算人の担保提供、清算人の報酬)
① 相続財産清算人は、「家庭裁判所から担保提供を命じられること」があり、他方、「清算人からの報酬付与申立に基づき、相続財産から相当の報酬を与えられること」があります。
② 相続財産清算人は、「相続財産法人(民法951条)」又は「将来出現するかも知れない相続人」のために管理、清算する業務を担当する者であるから、受任者と同様の地位にあるとされ、委任に関する諸規定が準用されます。
* 委任に関する諸規定の準用例
(ⅰ) 善管注意義務 (民法644条)
(ⅱ) 受取物引渡義務(民法646条)
(ⅲ) 金銭消費の責任(民法647条)
(ⅳ) 費用償還請求権(民法650条)
え 相続財産清算人が選任された後に、売買契約が締結され、所有権移転登記をする場合の手続
相続財産清算人は、所有権移転登記をする前提として、「相続財産法人化」の登記をする必要があります。
* 相続財産法人化の登記申請書の様式
登記の目的 | 所有権登記名義人氏名変更 |
原 因 | 平成29年5月5日 相続人不存在 |
変更後の事項 | 亡甲相続財産 |
申 請 人 | 秋田市山王一丁目〇番〇号 |
添 付 書 類 | 登記原因証明情報 代理権限証書 |
登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
第3 相続財産の清算人の報告(民法954条)
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければなりません。
第4 相続財産法人の不成立(民法955条)
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます。
* ただし、相続財産清算人がその権限内でなした行為の効力は、妨げられません。
ア 相続財産法人の消滅時期
出現した相続人が相続を承認した時です。
(理由)
相続放棄の場合を考慮した見解です。
イ 相続財産清算人の行為の効力
相続財産法人が遡及的に消滅したとしても、消滅までに清算人が行った権限内の行為については、その効力に影響を与えません。
第5 相続財産の清算人代理権の消滅(民法956条)
ア 代理権の消滅時期
相続財産清算人の代理権は、出現した相続人が相続の承認をした時に消滅します。
(理由)
相続人の出現と同時に代理権が消滅するとしなかったのは、出現した相続人による相続放棄の可能性もあるからです。
* 「相続の承認」の意義
相続の承認とは、下記のことである。
① 単純承認 (民法920条)
② 法定単純承認(民法921条)
③ 限定承認
イ 代理権消滅は、家庭裁判所の何らかの措置を要するか?
下記の2つの考え方があります。
① 必要説
家庭裁判所による「清算人の選任処分の取消し」があって、代理権が消滅する。
* 大阪高決昭40・11・30
② 不要説(この説が、妥当と解する)
相続人による「相続の承認」により、代理権は当然に消滅する。
* 大阪高決昭44・2・7
(理由)
家庭裁判所による取消し等がない限り、清算人の代理権が存続すると解することは、民法956条1項の明文に違反するだけでなく、遅滞なく管理計算を義務付ける同条2項の趣旨にも反するので、不要説が妥当と解する。
ウ 管理計算義務
相続財産清算人は、管理終了後遅滞なく、管理期間中に生じた一切の収支を計算し、相続人に報告しなければなりません。
第6 相続債権者及び受遺者に対する弁済(民法957条)
ア 債権申出の公告(相続財産清算人からの公告)
家庭裁判所が出した相続財産清算人選任の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての「相続債権者」及び「受遺者」に対し、2か月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。
・この公告期間は、相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内(6か月を下らない期間)に満了すべきものでなければなりません。
* ① 公告の具体的方法(官報)
官報により、「当該期間内(又は〇月〇日まで)に申出がなければ、清算から除斥される旨」を明記することを要します。
② 既に判明している「相続債権者」及び「受遺者」に対する催告
既に判明している「相続債権者」及び「受遺者」に対しては、個別的に、申出を催告することを要します。
・もし、これらの者が申出をしなくとも、清算から除斥されません。
イ 相続債権者及び受遺者への弁済
公告に定められた期間内に相続人が判明しないときは、相続財産清算人は、「その期間中に申出のあった、又は既に判明している相続債権者及び受遺者」に対して弁済をしなければなりません。
(ア) 具体的清算方法
下記の順序で配当されます。
① 優先権のある債権者
② 期間内に申出があったか、又は既判明の債権者
③ 受遺者
④ 期間内に申出がなく、判明しなかった債権者及び受遺者
(イ) 相続債権者等に対する弁済につき、相続財産(不動産等)を売却する必要があるとき
清算人は、相続財産(不動産等)を任意売却(家庭裁判所の許可を得て売却)又は競売手続により換価しなければなりません。
・もし、これらの者が申出をしなくとも、清算から除斥されません。
第7 権利を主張する者がいない場合(民法958条)
ア 民法952条2項の期間内(家庭裁判所が申し出る公告で、相続人があるならば一定の期間内に権利を主張すべき旨の公告。その期間は6か月を下ることができない。)に相続人としての権利を主張する者がいないとき相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません。
イ 6か月の公告期間が満了した場合
下記の者は、失権します。
① 相続人
② 清算人に知れなかった相続債権者
③ 受遺者
ウ 失権した相続人の権利等
(ア) 失権した相続人
失権した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産に対しても権利を有しません(最判昭56・10・30)。
・期間中に申出のあった債権者、受遺者に対する清算が未了のまま公告期間が終了したとしても、清算は続行されます。
・その場合、特別縁故者への分与は、残余財産の見込みに基づいて行われることも差し支えないが、国庫帰属は、清算の終了が前提で す。
(イ) 失権させられる権利
相続人の権利のほかは、弁済によって消滅する権利のみを意味します。
* したがって、賃借権、地上権、地役権など、清算人において清算できないような権利は消滅せず、対抗力を備えている限り、財産の分与を受けた特別縁故者又は最終的に国庫に承継されます(大判昭和13・10・12)。
第8 特別縁故者に対する相続財産の分与と請求公告(民法958条の2)
ア 特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の2)
民法952条2項の期間内(相続人捜索公告:期間6か月)に権利を主張する者がいない場合は、家庭裁判所は下記の者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます。
※この請求は、民法952条2項の期間満了後3か月以内にしなければならない。
(請求権者)
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
イ 相続財産分与者の詳細
(1) 被相続人と生計を同じくしていた者
(例)
(ⅰ) 内縁の配偶者
(ⅱ) 事実上の養親子
(ⅲ) 家族的な共同生活を送りながら相続人でない者
a 内縁の配偶者
b 内縁の夫
c 事実上の養親子
d 叔父・叔母
e 継親子
d 未認知の嫡出子
(ⅳ) 全くの他人の場合の肯定例
失業対策事業の日雇人仲間である被相続人と12年近く生活を共にし、同人の病気の療養看護に努めた者
(2) 被相続人の療養看護に努めた者
被相続人に対し、献身的に療養看護に尽くした者をいいます。同居人による看護の場合は、生計を同じくしていた者も該当することがあります。
(例)
(ⅰ) 被相続人のいとこの子
(ⅱ) 遠縁の関係がある者
(ⅲ) 民生委員・職場の同僚・元従業員
(ⅳ) 付添婦や看護師のように対価を得ている者でも下記のような場合は、「療養看護に努めた者」に該当します。
* この者は、原則的には、特別縁故者には当たりませんが、その看護振りや報酬額から見て、対価以上に尽力した者のことです。
(3) その他被相続人と特別の縁故があった者
(ⅰ) 一般的基準
「生計同一・療養看護」という例示に準ずる程度に密接な縁故関係がある者をいいます。
(ⅱ) 親族・隣人としての通常の交際
親族又は地域の隣人として、通常の付合いをしていたに過ぎないものは、特別縁故者に該当しません。
(ⅲ) 親族関係にある者による生活上・財産上の支援、貢献をしたことにより、縁故者として肯定された事例
a 被相続人の叔母の孫の夫が、被相続人の成年後見人となり、遠距離にもかかわらず多数回訪問して、被相続人の療養看護や財産管理に尽くし、費用を負担して葬儀供養を行った事例(大阪高決平2・10・24)。
b 被相続人の又従兄弟の妻が、被相続人の依頼により、任意後見契約を締結するなど精神的な支えとなり、死亡後は葬儀や墓守をし、有効な遺言の方式は備えていないものの、被相続人が申立人に相続財産を包括遺贈する旨のメモを残している事例(鳥取家審平20・10・20)。
c 被相続人の最も頼れる親族の1人であったとして、生計同一でなく、療養看護も経済援助もしなかった申立人(被相続人の亡父の実弟)の精神的援助を重視して特別縁故者と認めた事例(名古屋家審昭48・2・24)。
(ⅳ) 全くの他人の場合の肯定例
a 50年以上、被相続人と特に深い親交があった者(大阪家審昭38・12・23)。
b 被相続人のために家屋を購入してやり、かつ10年以上にわたり被相続人一家の生活を援助してきた被相続人の元雇い主(大阪家審昭41・5・27)。
(ⅴ) 法人等
法人も特別縁故者となることができます。
(例)
a 宗教法人
b 学校法人
c 社会福祉法人
d 地方公共団体
e 法人格なき社団・財団
被相続人が生活し、そこで死亡した養老院、養護老人ホーム
(4) その他、特別の縁故者に該当するかの問題とされた場面
(ⅰ) 過去の一時期の縁故
縁故関係は、被相続人の死亡時に存在している必要はなく、過去のある時期における縁故でもよい。
(ⅱ) 死後縁故
家事審判例は分かれ、否定例、肯定例があります。
* 死後縁故の許否に関連して、被相続人の死亡後の出生者が特別縁故者となり得るかの問題があります。
a 死後縁故につき否定説をとれば、この点も当然否定されるが、肯定説からは認められます。
b 肯定例として「大阪家審昭39・7・22」があります。
(ⅲ) 相続放棄をした相続人等
「相続放棄をした法定相続人」、「相続人不存在確定後に申し出た失権した相続人」が特別縁故者になり得るか?
法定相続人であったというだけでは、特別縁故者と認められるわけではありませんが、具体的な縁故関係があれば肯定されます(広島高岡山支決平18・7・20)。
(ⅳ) 分与を求める者が、被相続人の資産から不当に利得していた場合、その他
a 4年半の療養看護や葬儀の主宰はしたが、この過程で被相続人の資産を金1,200万円以上不当利得していた者につき特別縁故者とはいえないとした事例(さいたま家川越支審平21・3・24)。
b 被相続人の遺言を偽造した内縁の夫につき、分与の相当性を欠くとして否定した事例(東京高決平25・4・8)。
(ⅴ) 祭祀の主宰を行った者
「その他特別の縁故があった者」の審判例を見ていくと、被相続人の「葬儀」やその後の「法要」を主宰者として執り行ったという事情が「特別の縁故」の認定の一要素として掲げられていることが多い。
a 大阪高裁平成4年3月19日決定
被相続人の亡妻の姪3人につき、いずれも被相続人生前の関係は通常の親族としての交際の域を出るものではなく特別縁故関係は薄いとしつつも、「現在、被相続人の位牌を祀り、協力してその供養を行っていることを考えると、申立人らを特別縁故者とするのが相当であるとして、財産分与を認めています。
b 祭祀の主宰を行った者が、特別縁故者として分与が相当であると判断された審判例
被相続人の生前も通常の親族や知人の関係を超えた密な交流があり、精神的に支えてきたことも認めた上で特別縁故者と認めている。
* 祭祀を主宰したという事実は、生前の特別縁故関係の存否の程度を推測させる事情となり得るに留まる(鹿児島家審昭45・1・20)。
ウ 相続財産分与の相当性
(ア) 相続財産の分与
相続財産の分与は、家庭裁判所が分与を相当と認める場合になされます。
(イ) 分与の相当性の判断基準
民法に規定はないが、「縁故関係の内容、濃淡、程度、縁故者の性別、年齢、職業、教育程度」のほか、「残存すべき相続財産の種類、数額、状況、所在」等一切の事情を総合調査して決定します。
エ 相続財産分与の対象財産
特別縁故者に対して分与されるのは、「清算後残存すべき財産」です。
* 共有持分が、特別縁故者への分与の対象となるか?
判例(最判平元11・24)は、共有持分は、分与の対象となり、分与がなされないときに初めて、民法255条により他の共有者に帰属するとして、旧民法958条の3の優先適用説に立っています。
オ 相続財産分与申立の手続
(1) 申立
(ⅰ) 申立権者
申立権を有するのは、特別縁故関係を主張する者です。
* a 自己への分与を求めることを要し、自己以外の者への分与を求めることは許されません。
b 相続財産清算人自身が子の申立をした場合
相続財産清算人としての職務の公正さが疑われることになるので、家庭裁判所は職権により、相続財産清算人を解任すべきものと解されています。
(ⅱ) 特別縁故者の地位の承継
a 特別縁故者と考えられる者が、分与の申立をしないで死亡したとき
相続人は、その地位を承継することができません(東京高決平16・3・1)
b 特別縁故者として分与を受ける権利
家庭裁判所の審判により形成されるものであり、特別縁故者と主張する者が、分与を受ける前に、「遺言無効確認の訴」を提起する訴えの利益を有することは認められません(最判平6・10・13)。
c 分与申立後に死亡したとき
一種の期待権となるから、相続されるとする裁判例が多数です。
(ⅲ) 裁判管轄
a 原則
相続開始地の家庭裁判所です。
b 事情によっては
他の裁判所への申立も許されます。
* 先に管理人を選任し、相続権主張(相続人捜索)の公告をした家庭裁判所に申し立てることが望ましいとされています。
(理由)
「数人からの分与申立の場合の併合審理の要請」や「相続財産清算人との連絡の必要」からです。
(ⅳ) 申立期間
分与の申立は、民法952条の「相続権主張(相続人捜索)の公告期間(6か月)」満了後3か月以内にすることを要します。
* この申立期間の遵守につき、下記の2つの場面で問題があります。
a その始期である「相続権主張(相続人捜索)の公告期間(6か月)」の満了より前に申立ができるか?
適法と解されています。
b 期間満了から3か月という期間経過後の申立が許されるか?
3か月の期間経過後の申立は、不適法とされています。
(2) 審判手続
(ⅰ) 通知・併合審理
a 通知
分与の申立があったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を相続財産清算人に対し通知しなければなりません。
b 併合審理
数人から分与の申立があったときは、審理手続、審判は併合して行うことを要します。
(ⅱ) 事実調査・意見聴取・換価
a 原則
審判の基礎となる資料については、家庭裁判所が、職権で事実調査を行い、また、必要と認める証拠調べを、「申立」により又は「職権」で行って収集します。
b 調査嘱託・照会
家庭裁判所は、他の家庭裁判所や簡易裁判所、関係官庁や銀行等に対する調査の嘱託、照会ができ、家庭裁判所調査官に対して事実調査を命ずることができます。
c 意見聴取
家庭裁判所は、相続財産清算人の意見を聴取しなければなりません。
(ⅲ) 審判
a 審判の方法
家庭裁判所は、「相続財産の内容、申立人と被相続人との縁故関係の内容・程度」を判断基準として、「申立人が特別縁故者に該当するか、分与が相当か、一部分与か、全部分与か、分与の内容、数額」を決定します。
b 審判の確定
分与の審判が確定すると、特別縁故者は、その財産を取得し又は取得し得る地位に就くが、この取得の法的性質は、被相続人からの相続によるものではなく、相続財産法人からの無償譲渡となります。
第9 残余財産の国庫への帰属
ア 残余財産の国庫帰属(民法959条)
下記の場合は、相続財産は、国庫に帰属します。
① 特別縁故者への分与手続において、特別縁故者からの分与申立がないとき。
② 特別縁故者への分与が一部に留まり、残余財産があるとき。
イ 国庫帰属の法的性質
国庫に帰属するとは、国家に帰属するという意味です。
* ① 国庫に帰属する趣旨
その趣旨は、法人となった相続財産が、清算手続を経て国庫に帰属するのであり、国庫が相続人の地位を承継するのではありません。
② 国庫帰属が決まった場合
相続財産清算人は、管理計算をして、相続財産を国庫に引き継がなければなりません。
ウ 国庫帰属の時期
国庫帰属の時期については、下記の2つの説がありますが、判例は、「国庫引継時説」を採用していますので、実務では、「現実に残余財産が引き継がれた時を国庫帰属の時期」としています。
① 国庫引継時説(最判昭50・10・24)
現実に残余財産が引き継がれた時を、国庫帰属の時期とします。
* (ⅰ) 相続財産法人の消滅
相続財産全部の引継ぎが終了するまでは、相続財産法人は消滅せず、管理人の代理権も存続します。
(ⅱ) 国庫への引継手続
国庫への引継手続は、財産の種類により異なるが、それぞれが完了したときは、相続財産清算人は、家庭裁判所に対し、管理終了報告書を作成し、提出します。
② 審判確定時説
特別縁故者による分与申立期間満了時又は分与申立の却下ないし一部分与の審判の確定時が国庫帰属の時期であり、同時に相続財産法人は消滅し、清算人の代理権も消滅します。
* この説の弱点
この説によると、「(ⅰ)現実には、分与審判が確定した時点で清算が完了していない場合」や「(ⅱ)現実に財産が国庫に引き継がれるまでに時間が掛かる場合」の不都合が指摘されています。
第10 相続財産清算人の清算終了
ア 清算終了事由
相続財産清算人の代理権が消滅し、清算事務が終了するのは、下記の場合です。
① 民法上の管理終了事由の発生
残余財産を国庫に引き継ぐ前に、相続人が現れたときです。
② 下記の引継行為等により、管理財産を引き継いで管理財産が無くなったとき
(ⅰ) 特別縁故者への財産の引継ぎ
(ⅱ) 相続財産の破産開始決定による破産管財人への財産の引継ぎ(破産法30条、223条)
(ⅲ) その他の引継ぎ等の行為により管理財産が無くなったとき
イ 清算終了報告
相続財産清算人は、清算が終了したときは、残余財産を国庫に引き渡した後に、家庭裁判所に清算終了報告書を提出しなければなりません(民法959条、956条2項)。
* 清算に係る計算
清算に係る計算は、清算終了報告書をもって充てます。
第11 遺贈を受けた者の税務問題
相続人全員が、相続放棄をしたときは、取得する財産が無いことになるので、相続税が課税されません。
* 注意事項
ただし、「生命保険金」、「死亡退職金」等のみなし財産の遺贈を受けたときは、遺産に係る基礎控除額を超えた分については相続税が課税されます。
(課税の詳細)
「相続税法上のみなし財産(生命保険金・死亡退職金等)」については、相続放棄をした者も受け取ることができます。
・しかし、相続放棄者は、相続人ではないので、遺贈により取得することになります。
* したがって、相続放棄者には、みなし財産についての非課税規定は適用されません。
・遺贈による合計額が、遺産に係る相続税の計算上、基礎控除額を超えるときは、相続税の課税がなされます。