お電話でのお問い合わせ:018-864-4431
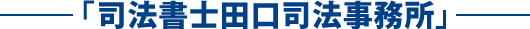

(当事務所の取扱業務)
① 不在者の財産管理人選任申立
② 供託業務
③ 不在者管理業務
(目次)
(1) 不在者の財産管理
ア 不在者の財産管理人の意義
イ 不在者の財産管理人の選任
ウ 不在者の財産管理人の職務
エ 不在者の財産管理の終結
(2) 不在者の財産管理人の処分行為
(1)不在者の財産管理
ア 不在者の財産管理人の意義
不在者の財産管理人とは、従来の住所又は居所を去り、容易に帰来する見込みのない行方不明者(不在中に財産管理人の権限が消滅した場合を含む。)の財産を管理するため、家庭裁判所の選任により、管理、処分の権限を付与された法定代理人のことです(民25条~29条)。
イ 不在者の財産管理人の選任
(ア) 選任の要件
選任の要件は、下記のとおりです。
① 財産を有する者が、「(ⅰ)その財産の管理人を置くことなく、従来の住所又は居所を去ったこと」又は「(ⅱ)本人の不在中に管理人の権限が消滅しこと」(民法25条1項)。
② 利害関係人又は検察官から申立てをすること。
* A 利害関係人とは
不在者の財産管理について、法律上の利害関係を有する者のことです。
B 利害関係人の具体例
a 不在者の共同相続人
b 不在者の債権者
c 不在者の財産を時効取得した者
d 不在者所有不動産の隣地所有者
e 不在者の債務者等
(イ) 管轄裁判所
不在者の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所です。
* ① 不在者の住所が日本にないとき、又は日本における住所地が不明のときの管轄裁判所
不在者の居所地を管轄する家庭裁判所です。
② 居所も不明なときの管轄
不在者の居所地を管轄する家庭裁判所です。
不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(家手145条)。
③ 申立をした裁判所と財産管理の対象となる不在者の財産の所在地が異なるときの管轄
不在者の財産の所在地を管轄する家庭裁判所に移送することを求める旨の上申書を提出するよう裁判所から促されることがあります。
(ウ) 管理費用の予納
① 「不在者の財産の管理に要する費用」や「不在者財産管理人の報酬」等は不在者の財産の中から支弁することになっています(家手146条2項、民法29条2項)。
② 上記①が原則ですが、清算して初めて不在者の財産から支弁できるかどうかが判明するので、それまでの間の費用として、申立人があらかじめ費用を予納することが必要です。
・なお、不在者の財産で管理費用を賄えた場合は「予納した費用」は返還されます。
* A 費用の予納
不在者財産管理人選任申立の際に、その費用を予納することが求められます。
B 予納金の額
管理すべき財産の価額等を考慮して算出されます。
C 不動産のみの遺産分割協議のための管理人選任を求る場合の予納金の額
不在者が受けるべき代償金の範囲内で決定される場合もありますが、申立の際に裁判所と協議をしておくのがよいでしょう。
ウ 不在者の財産管理人の職務
(ア)不在者の財産管理人の権限
不在者の財産管理人は、不在者の法定代理人とされますが、権限の定めのない代理人と同様の権限を有します(民法28条)。
* ① 権限の定めない代理人の権限の具体例(民法103条)
(ⅰ) 保存行為
(ⅱ) 管理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内での利用又は改良行為
② 上記A、Bの範囲を超える行為をする場合は、家庭裁判所の許可を必要とします。
(イ) 財産目録の作成
① 管理人の財産目録の作成
管理人は、管理すべき財産の目録を作成しなければなりません(民法27条1項)。
* 家庭裁判所は、管理人に対して不在者の財産の保存に必要と認める処分を命じることができます(民法27条3項)。
② 管理人の財産状況の調査
* 財産状況とは
例えば、「不動産の租税公課・損害保険料・地代家賃の収支状況」等のことです。
③ 家庭裁判所に対する報告
管理人は、就任後一定期間内に家庭裁判所に対して、財産目録を作成の上、財産目録や収支状況等を報告しなければなりません。
* 管理が長期にわたるとき
一定期間(年1回程度)ごとに、家庭裁判所に管理の報告をすべきです。
(報告を怠っていた場合)
家庭裁判所から、民法27条3項の処分命令を伴う報告を求め られることになります(家手146条2項)。
(ウ) 不在者の財産管理人の権利義務
不在者の財産管理人は、家庭裁判所の処分命令(民法27条3項)、担保提供命令(民法29条1項)に服するほか、下記の義務を負い、かつ権利を有します。
(ⅰ) 義務
A 善管注意義務(民法644条)
B 受取物の引渡義務(民法646条)
C 金銭消費の責任(民法647条)
(ⅱ) 権利
費用償還請求権(民法650条)
(エ) 権限外行為(例:遺産分割協議)の許可申立
A 許可申立が必要な場合
家庭裁判所の選任に係る不在者財産管理人は、民法103条に定める「保存行為」と「利用・改良行為」しかなし得ないので、それ以外の行為を必要とするときは、不在者財産管理人が申立人となって権限外行為(遺産分割協議等)の許可の審判を家庭裁判所に申し立てることになります。
B 許可の例示(遺産分割協議の場合)
(ⅰ) 遺産分割協議の許可の審判の申立に当たって
遺産分割協議の案に、「不在者を含めた各相続人の法定相続分、各相続人の特別受益、寄与分等を勘案した具体的取得額」を明らかにする必要があります。
(ⅱ) 裁判所の審査
不在者が、理由のない不利益を受けることのないように具体的な内容について審査されます。
(ⅲ) 遺産分割協議書案の作成
不在者の特別受益が立証されている場合を除いて、不在者が法定相続分に応じた価額を得ることを内容とする遺産分割協議書案を作成する必要があります。
(ⅳ) 遺産分割の対象となる相続財産が不動産のみで、現物分割が社会的常識からいって不可能と認められる場合
代償分割又は換価分割の方法を採ることになります。
エ 不在者の財産管理の終結
(ア) 財産管理の終結
権限外行為(遺産分割協議)の許可の審判がなされた場合には、遺産分割協議書案に基づいて、他の相続人全員とともに遺産分割の協議を行い、分割協議を成立させることになります。
* 遺産分割協議のための不在者財産管理業務
遺産分割協議の成立をもって、その目的を果たすわけですが、これをもって、財産管理が当然には終了するわけではありません。
(イ) 家庭裁判所は、下記の場合は、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立により、又は職権で、民法25条1項の規定による「管理人の選任」、その他「不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判」をしなければなりません(家手147条)。
① 不在者が、財産を管理することができるようになったとき。
② 財産の管理を継続することが相当でなくなったとき。
(ウ) 遺産分割協議が成立して、管理人が遺産又は代償金若しくは換価金を受け取ったとき
管理財産が存するので、処分取消審判の申立要件を欠き、管理人による財産管理業務は継続します。
(具体的業務内容)
A 不在者が帰来したとき
遺産又は代償若しくは換価金を支払う旨を協議内容とすることができるかが検討されます。
B 「帰来時の弁済」の許否
家庭裁判所の担当裁判官の判断によります。
C 「帰来時の弁済」が許可された場合
管理人による財産管理業務を終わらせることができます。
D 「帰来時の弁済」が許可されない場合
管理財産が、管理人の報酬を賄うに相当な額か、あるいは満たない額である場合は、管理人から報酬付与審判の申立てをさせ、管理財産と同等額を報酬として付与する旨の審判をして、不在者の財産を無にして財産管理業務を終結させることもあります。
(2) 不在者の財産管理人の処分行為
財産の売却、遺産分割等の財産の処分を必要とする特別の事情がある場合は、家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人権限外行為許可申立」をして、その許可を受ける必要があります(民法28条)。主な権限外行為は、下記のとおりです。
① 遺産分割
② 保険の解約
③ 不動産の処分(不動産賃貸、建物の取壊し等)
④ 動産の売却、譲渡、贈与、廃棄(自動車の売却、廃車手続を含む。)
以上