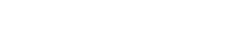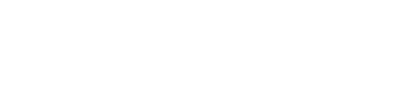今回も民法の回です。
前回に引き続き、「売買」についてお話をします。
売買に付随する契約として、手付のほかに「買戻し」という制度があります(民法第579条~第585条)。
買戻しとは、たとえばAが所有する土地をBに売却する際、それと同時に、「後日、Bの払った代金及び契約費用をAがBに返還して、Aが当該売買を解除する」旨の特約をすることをいいます。
ただし、買戻しには、①対象は不動産のみ、②権利行使できる期間は最長10年(期間を定めなければ5年以内)、③第三者に対抗するには登記が必要、といった一定の制限がかけられています。
買戻しは、債権の担保として用いられます。つまり、AがBからお金を借りる場合、自分の土地をBに売却し、その代金として金銭を得ます。そして買戻期間内に、AはBに代金及び契約費用を返還して、売却した土地を取り戻します。仮にAが返還できなかった場合には、Bは土地の所有権を取得できますので、Bは安心してお金を貸すことができます。
民法起草者は、金融の世界で古くから行われていた買戻しを容認せざるを得なかったものの、上記のような制限をかけることで、できるだけ買戻しの規制を図りました。
ところが、実務上、制限の多い買戻しの代わりに「再売買予約」という方法を用いることで同一の目的を達成でき、判例が再売買予約を有効と認めたことから、買戻しに対する規制は潜脱されることになってしまいました。
再売買予約とは、たとえばAがBに売却したA所有の土地を、将来BがAに売り渡すこと(再売買)の予約をいいます。AがBに代金+αを支払えば、Aは予約完結権を行使することができ、土地を取り戻すことができます。
再売買予約は、対象も不動産に限らず(実務上は、登記ができる不動産について運用されています)、権利行使できる期間も自由(期間を定めなければ10年)で、仮登記で第三者に対抗することができるなど、買戻しに比べ制限が緩くなっています。
今朝のお供、
The Beatlesの『Please Please Me』。
友人がビートルズのBOXセットを購入したとの話を聞き、影響されました。これが時代を変えた瞬間の音。タイトルのレトリックも秀逸です。
(佐々木 大輔)
今回は民法の回です。
今回から数回にわたって、民法555条の「売買」についてお話をさせていただきます。
「売買」とは、当事者の一方(売主)がある財産権の移転を約束し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを約束すれば成立します。コンビニでおにぎりを買う場合など、皆さんにとって最も身近な契約ではないでしょうか。
コンビニのおにぎりからマイホームまで、売買契約の対象は様々ですが、高額な売買契約の場合、簡単に契約を解除されては困ります。
そこで、我が国の民法では、売買に付随する契約として「手付」(557条)という契約を定めています。
「手付」とは、売買などの契約の際、一方から他方へ(売買の場合は買主から売主へ)支払われる金銭や有価物をいいます。手付の額は、代金の1割から2割が相場とされているようです。
手付にはさまざまな機能がありますが、主なものとして、契約成立の証拠とされる証約手付、解除権留保の対価とされる解除手付、債務不履行の場合の違約金とされる違約手付があります。
ところが、この手付、契約の際にどのような趣旨の手付であるかが定められていない場合がけっこうあるのです。そのため、差し入れられた金銭がそもそも手付であるのか、また、手付であるとしてどのような趣旨の手付であるのか、という問題が生ずるのです。
まず、手付であるかについては、その金額の多少によって判断されることが多いようです。代金の半分を差し入れたとなれば、それは手付というより債務の一部履行と考えるのが自然でしょう。
次に、どのような趣旨の手付であるかについて、民法557条は、「当事者の一方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して解約が可能、売主は手付の倍額を買主に返して解約が可能」と定めていますので、原則として解約手付であると解釈されます。ただし、この規定は任意規定であるため、これと異なる趣旨の手付の合意も禁止されていません。そこで、ある手付の合意がなされた場合、557条の解約手付の趣旨を排除するものであるのかどうかが問題となります。この点について判例は、違約手付の合意があった事案について、その手付は同時に解約手付でもあり得るという判断を示しました。
最後に557条について、「履行の着手」、「当事者の一方」の意義をどのように考えるかという問題が残ります。
判例は、この問題について、履行の着手とは「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供に不可欠な前提行為をすること」という基準を示しました。
そして、履行に着手する「当事者の一方」とは誰のことなのかについては、解除される側のみを指し、自ら履行に着手した者は、相手方が履行に着手するまでは解除権を行使できると判断しています。
今朝のお供、
The Stone Roses(イギリスのバンド)の『The Stone Roses』。
再結成の話題で持ち切りですね。
(佐々木 大輔)
今回から、民法典に規定されている13個の典型契約についてお話をさせていただきます。
条文の順番どおり、「贈与」から。
民法549条以下に規定されている贈与契約とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で自己の財産を与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
贈与の撤回については、書面によって贈与契約をしたか否かによって結論が分かれます。
書面による贈与の場合、撤回することはできません。
書面によらない贈与の場合、「履行の終わった部分」を除いて、撤回することができます。不動産の贈与は、引渡しまたは所有権移転登記のいずれか一方がなされれば、履行が終わったものと考えるのが裁判所の判断です。
贈与契約は無償契約ですから贈与者は原則として担保責任(契約の目的物に欠陥があった場合、それを給付した者が負う損害賠償などの責任)を負いません。しかし、贈与者が贈与の目的物に瑕疵(本来備わっているはずの機能が備わっていないこと)があることを知りながら、そのことを受贈者に告げなかった場合には、担保責任を負います。
以上が一般的な贈与ですが、その他いくつか特殊な贈与がありますので、それらをみていきましょう。
まず、「定期贈与」があります。これは、定期の給付を目的とする贈与のことをいい、たとえば毎月10万円ずつ仕送りをするという内容の契約があります。定期贈与は人的関係を基礎としていることがほとんどですので、特約がない限り、贈与者または受贈者の死亡によってその効力は失われます。
「負担付贈与」とは、受贈者をして一定の給付をするべき債務を負担させる贈与契約をいいます。
たとえば、AがBに家屋を贈与する代わりに、BがAの面倒を見るという内容の契約です。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことをいいます。
死因贈与と似ているものに「遺贈」がありますが、死因贈与は契約であるのに対し、遺贈は単独行為(贈与者の一方的な意思表示のみによって成立する)という点で異なります。
とはいえ、死因贈与も遺贈も、本人の死亡により効力が生ずるという共通点があるので、その性質に反しない限り、死因贈与も遺贈と同じように考えることができます。
今朝のお供、
COLDPLAY(イギリスのバンド)の『MYLO XYLOTO』。
“ロックの”と限定する必要もなく、今年最大の目玉ではないでしょうか。傑出した1曲が引っ張るアルバムというより、全ての曲が美しく融和しているアルバムです。
(佐々木 大輔)