お電話でのお問い合わせ:018-864-4431
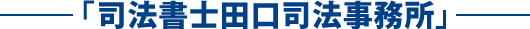

(当事務所の取扱業務)
① 契約書等各種文案書類の作成代理、契約書等各種文案書類作成の相談
② 非紛争的事案についての契約締結代理
③ 就業規則・規程等の作成
(目次)
(1) 契約書の意義等
① 契約の意義
② 契約書作成の目的
③ 裁判の証拠としての活用
④ 公正証書としての活用
(2) 契約書作成について
① 契約の種類
② 契約書の記載事項
(3) 契約書等の種類と業務
① 当事務所が取り扱っている「契約書等に関する業務」の詳細
② 非紛争的な事案に関する「契約書・協議書の作成」に当たって
(4) 契約書に類似する表題(タイトル)の書面(契約書・覚書・念書・協定書・約款)
(5) 電子契約書
(1) 契約書の意義
ア 契約の意義
契約とは、一定の法律効果の発生を目的とする、2人以上の相対立する意思表示の合致(合意のこと)により成立する法律行為のことです。
・別の表現をすると、「いずれかの当事者が、約束した義務を履行しなかった場合に、約束を守ってもらえなかった当事者が、裁判所に対して救済を求めることができる当事者間の約束です。
* 用語の説明
① 法律行為の意義
権利の得喪変更を目的とする、意思表示を要素とする合法的な行為のことです。
・契約は、その典型です。
・法律行為には、「単独行為(例:遺言)・合同行為(会社設立行為・組合契約)」も含まれます。
② 不法行為の意義
故意・過失により他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる(民法709条)。
イ 契約書作成の目的
(ア) 紛争の予防
口頭での契約では、「契約の有無、内容」関して、後日紛争が生じる可能性が大です。そこで、契約を書面にし、保有しておくことにより容易に紛争を避けることができます。
(イ) 債権の管理・回収
契約の主要目的は、債権の管理・回収にあります。
ウ 裁判の証拠としての活用
訴訟になった場合、債権の存在を立証する必要がありますが、その際、契約書が証拠書類としての役割を果たすことになります。
エ 公正証書としての活用
契約書を強制執行認諾付公正証書(公証人の作成する公文書)で作成することにより、債権の速やかな回収を図ることができます。
* 判決を得なくとも公正証書で強制執行することができます。
(2) 契約書作成について
ア 契約の種類
民法には、13の典型契約が規定されています。この「13の典型契約」のうち、主に利用されるのは下記の契約です。
記
① 売買契約
② 金銭消費貸借契約
③ 賃貸借契約
④ 請負契約
⑤ 労働契約
⑥ 委任契約
イ 契約書の記載事項
(ア) 契約書には、契約一般に必要な契約条項がありますが、その他に各契約に必要となる要件があります。
あ 契約書の一般的な契約条項
① 契約締結の目的
② 合意内容
③ 契約目的の履行方法(目的物の引渡し方法)
④ 対価の支払方法
⑤ 契約期間・期間満了後の更新
⑥ 契約当事者の付随的義務
⑦ 期限の利益喪失
⑧ 契約の解除
⑨ 守秘義務
⑩ 債務不履行の場合の事後処理
⑪ 裁判管轄(合意管轄)
⑫ 誠実協議事項
い 特別記載事項
① 担保権設定条項
② 競業避止条項
③ 反社会的勢力条項
(イ) 基本契約書と個別契約書の記載事項
あ 基本契約書
商人間では継続的に売買することや継続的に役務を提供することを目的とする取引がなされています。
・この場合、継続的取引全体に適用される基本的事項をあらかじめ取りきめておく場合が多々あります。この契約書を基本契約書といいます。
・基本契約が締結されていれば、売買の個別契約に当っては、「商品の数量、価格、納期等」を合意すればよいし、日常的な取引では、「注文書・注文請書」を、ファクスのやり取りでなすこともできます。
(基本契約書の主な契約条項)
① 個別の売買契約締結方法
② 価格の算定方法、商品の納入方法、代金の支払方法
③ 検査の条件(検査方法、検査基準、検査時期)
④ 危険負担
⑤ 所有権の移転時期
⑥ 瑕疵担保責任及び品質保証条件
⑦ 免責条件
⑧ 債務不履行があった場合の対策
⑨ 損害賠償、損害担保
い 個別契約書
個別契約書とは、個別の内容を記載した契約書のことです。
(個別契約書の主な記載事項)
(あ) 売買契約
① 商品明細(品名、品質、数量)
② 価格(単価、総額)
③ 納入条件(引渡時期、方法、場所、包装内容)
④ 売買代金の支払条件(支払時期、支払方法)
(い) 請負契約
① 工事名、工事内容
② 工事場所
③ 工期
④ 工事代金
(3) 契約書等の種類と業務
ア 当事務所が取り扱っている「契約書等に関する業務」の詳細
当事務所は、各種契約書等の文案作成・作成相談・作成済み契約書の内容をチェックいたしております。
・下記は、日頃、当事務所が作成を依頼されている主な契約書等の例ですが、その他にも種々の契約書等を作成しております。
(主な契約書等)
① 金銭消費貸借契約書(借用書)
② 贈与契約書(定期贈与、負担付贈与、死因贈与)
③ 土地売買契約書・建物売買契約書
④ 不動産譲渡担保権設定契約書
⑤ 土地賃貸借契約書・建物賃貸借契約書
⑥ 事業用定期借地権設定契約書・定期借家契約書
⑦ 動産売買契約書(家具・機械類等の売買)
⑧ 動産質権設定契約書・動産譲渡担保権設定契約書
⑨ 債権譲渡契約書
⑩ 債務承認弁済契約書・債務免除証書・債権放棄書・債務不存在確認書
⑪ 離婚協議書・財産分与契約書
⑫ 抵当権設定契約書・根抵当権設定契約書
⑬ 継続的取引基本契約書
⑭ 業務委託契約書(商品販売等)
⑮ 請負契約書(建物建築工事その他)・建築工事予防協議書
⑯ 雇用契約書・労働契約書
⑰ 委任契約書・準委任契約書
⑱ 身元保証契約書
⑲ 和解契約書・示談書
⑳ 遺言書
㉑ 遺産分割協議書
㉒ 合意書・覚書・確認書
㉓ 会社・法人設立に当り必要な書類(発起人会議事録・創立総会議事録・取締役会議事録・定款・株式申込書など)
㉔ 会社・団体の議事録及び会議資料
㉕ 就業規則等の約款
㉖ 警察機関あての告訴状・告発状、ストーカー行為警告書、嘆願書・陳情書・上申書
㉗ 介護利用関係に関する契約書
㉘ 家族信託契約書(民事信託)
㉙ 終活に関する契約書(見守り、死後事務委任等)
イ 非紛争的な事案に関する「契約書・協議書の作成」に当って、行政書士の業務範囲である「契約締結代理業務」として、下記のような「話合い・協議」の業務も取り扱っています。
① 交通事故示談の協議と示談書作成業務
事故の責任を自認する加害者と、事故の過失割合や損害賠償金等の「話合い・協議」を被害者から受任した範囲で代理し、合意の示談書をまとめて自賠責保険金の支払請求につなげること。
② 遺産分割協議と遺産分割協議書作成業務
相続人間に調停・訴訟の因をなす紛争状態がなければ、行政書士は、助言説得を含めて相続人間の合意形成をリードし、遺産分割協議をまとめる代理行為ができます。
・そうした場合、両当事者や複数当事者の代理を務めて契約書・協議書を作成することも「民法第108条の双方代理禁止規定」に触れません。
ウ 公正証書による契約書作成業務
(ア) 契約書によっては、公正証書による作成が必要なものがあります。
例えば、「事業用定期借地権設定契約書・公正証書遺言(自筆証書遺言と違い、家庭裁判所の検認手続が不要)」です。
(イ) 金銭の支払を目的とする契約書で、債務者が強制執行に服することを予め認諾しているときは、勝訴判決と同様の効力をもつので、その公正証書を利用して強制執行をすることができます。
(ウ) 公正証書による作成が必要でなくても、公正証書を作成することにより、証拠力を高めたり、後日の紛争を予防する資料とすることができます。
(4) 契約書に類似する表題(タイトル)の書面(契約書・覚書・念書・協定書・約款)
ア 契約書の意義
契約とは、相対立する2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のことあり、この内容を書面化したものが契約書です。
つまり、契約とは、当事者の一方の「申込み」と他方の「承諾」によって成立する法律行為のことです。
* ① 書面の実態が契約の内容となっているものの取扱い
書面の表題(タイトル)はどうあれ、書面の内容が契約の基本を定めたものである場合は、契約書としての取扱いとなります。
② 法律行為とは
法律行為とは、権利の得喪変更を目的とする「意思表示を要素とする合法的行為」のことです。
③ 権利の得喪が生じる原因は
(ⅰ) 人の行為
A 法律行為
契約・単独行為(例えば遺言)・合同行為(例えば会社設立)
B 不法行為
(ⅱ) 事件
時効・附合・事件
イ 覚書の意義
覚書とは、「① 契約書を作成する前の段階で、当事者双方の合意事項を書面化したもの」や、「② 既にある契約書を補足したり、変更したりした書面のこと」をいいます。
* ① 覚書作成の実情
覚書は、実態は契約だとしても、相手方との間で、柔らかい表題を付した書面を作成して、物事を解決しやすくする場合などに用いられる表題です。
② 覚書の実態が契約書の場合
印紙の貼付が必要な場合もあります。
③ 確認書について
確認書という表題で作成された書面は、実態上「覚書」と同一の意味を持つことが多いです。
ウ 念書の意義
形式的には、一方の当事者が、他方当事者に対して差し入れる形式をとった書面のことをいいます。
そのため、書面には、念書を差し出した当事者の署名・押印しかありません。
* ① 念書の内容
内容は、自由で幅広く、「わび状のような契約の実質を備えていないもの」や「念書を書く者が、一方的に義務を負担したり」、「一定の事実を認めたり」するような内容のものもあります。
② 念書の効用
トラブルが生じたときの証拠となります。
③ 念書の例
借用書・誓約書・確約書等
エ 協定書の意義
一般的に、契約当事者間で基本的事項を約定した基本契約書ができており、その基本事項の具体的な細目を定める書面として作成されるものです。
オ 約款の意義
(ア) 約款の意義
多数取引の画一的な処理のため、あらかじめ定型化された契約条項(又 は条項群)のことをいいます。
・約款は、普通取引約款・普通契約条款とも言われます。
* 代表的な約款例
① 普通保険約款 |
② 運送約款 |
③ 銀行取引約定書 |
④ 倉庫寄託約款 |
⑤ 建築請負約款 |
⑥ ホテル宿泊約款 |
⑦ 条項群全体若しくは個々の条項を意味することもある約款 (ⅰ) 免責約款 (ⅱ) 期限の利益喪失約款 |
||
(イ) 約款の拘束力の根拠
約款は、当事者間の事前の十分な交渉を期待できないにもかかわらず、妥当性があるとされています。
・その根拠は、判例の主流的な考え方である「意思推定説」にあります。
* 意思推定説の考え方とは(判例の主流)
取引の相手方が、約款によらない旨の意思を表示しないで契約したときは、反証がない限り、約款による意思をもって契約したものと推定する。
(ウ) 約款の解釈
① 客観的解釈・合理的解釈
約款では、通常の合意と異なり、個別具体的な両当事者の一致した意思を探求することよりも、当該約款の利用が予定される取引圏の平均的かつ合理的な顧客の理解を基準とする「条項の客観的・合理的な意味内容」の確定が重要となります。
② 約款設定における一方的性格
約款の設定は一方的であるため、下記のような解釈・原則があります。
(ⅰ) 制限的解釈
約款設定者の責任を制限・免除する条項(免責条項)や顧客に義務を負担させる条項については、限定的に解すべきとする解釈です。
(ⅱ) 不明確準則・作成者不利の原則
多義的な条項については、顧客に有利な解釈をすべきとする原則です。
(エ)約款の規制
約款には、顧客にとって不利な条項が一方的に挿入される危険性が常に伴うため、司法・行政・立法面での規制が課題とされています。
* 近時の方向性
近時、消費者契約法等により、一定の不当条項を無効とする実体法上のルールが整備されつつあります。
(5) 電子契約書
ア 電子契約とは
「① 電子ファイルをインターネット上で交換」して「② 電子署名を施す」ことで契約を締結し、企業のサーバーやクラウドストレージなどに「電子データを保管しておく契約方式」 のことです。
* 2001年以降、「電子署名法」や「電子帳簿保存法」といった電子契約に関する法的環境が整備され、電子署名やクラウドストレージ等の技術的開発も進んでおり、電子契約を導入しやすい環境になりました。
・日本の商慣習において当たり前に行われてきた「紙」と「印鑑」による契約締結だけでなく、電子契約による契約締結も徐々に増加してきています。
イ 電子契約のタイプ別分類
電子契約サービスには、大きく分けて2つの型があります。
① 当事者署名型
② 事業者署名型
これを更に細かく分類すると、以下3つの署名タイプに分類することができます。
(ア) ローカル署名
秘密鍵の保管と電子署名生成処理を、本人の管理下で行うものです。
(イ) リモート署名
秘密鍵をサーバーに預け、本人がサーバーに指示して電子署名を生成するものです。
(ウ) クラウド署名
サーバー等が、立会人や目撃者の立場で電子署名を生成するものです。
* 2001年の電子署名法施行時は、当事者署名型が主流でしたが、2015年以降は、事業者署名型の電子契約サービスが普及し、主流の電子契約サービスとなりました。
(理由)
法的な有効性を保ちながら、利用者による署名鍵の準備や電子証明書の発行手続に関する手間やコストなく利用できる点で、事業者署名型が企業のニーズに合致しているためです。
ウ 書面契約と電子契約の比較
書面契約と電子契約との比較は、下記のとおりです。
| 分類 | 書面契約 | 電子契約 |
|---|---|---|
| 書類媒体 | 紙への印刷 | 電子データ |
| 署名方法 | 記名(署名)、押印 | 電子署名 |
| 締結日時の証明 | 日付記入、確定日付の取得 | 認定タイムスタンプ |
| 相互確認 | 原本の郵送、持参による受渡し | インターネット上での電子データによる受渡し |
| 保管方法 | 倉庫やキャビネットによる原本の物理的な保管 | 自社内のサーバーや外部のデータセンターによる電子的な保管 |
* 電子契約における企業間取引のメリット
① 契約に関する費用の削減(印紙税、紙不要等)
② 契約締結スピードと管理の業務効率向上
③ 契約に関する各種コンプライアンスリスクの低減
エ 電子署名とは
電子署名とは、印影や手書署名に代わって電子ファイルの作成者の証明をしやすくするとともに、「① 電子ファイル作成者」と「② 作成後にファイルが改変されていないこと」を推定できるようにした仕組みが、一般に「電子署名」と呼ばれているものの正体です。
* 現在、この電子署名を実現する主な方法として、暗号技術を用いた公開鍵暗号方式が用いられています。
・電子契約サービスの利用者は、難しい知識や操作は不要です。
オ 電子契約と電子署名に関する主な法令
電子契約に関わる法的環境は、2000年以降順次整備されています。以下、代表的な法律について紹介します。
① 民法
令和2年4月に施行された改正民法に、「契約方式の自由」が明記され、「契約の成立に、書面は必要ない」という大原則が明文化されました(民法522条2項)。
② 電子署名法
「押印や直筆署名に代えて、電磁的な同意の記録を、電子ファイルに行った者を明示する」とともに、「作成時以降、データが改変されていないことを検知し、担保できる技術的措置」を、電子署名と定義した法律が電子署名法です(電子署名法2条1項)。
* この電子署名を本人が電子ファイルに施すことで、電子化された契約書等の真正な成立が認められることになります(電子署名法3条)。
* クラウドサインは、この電子署名法に準拠したクラウド型電子契約サービスであるとの確認を、主務官庁より日本で初めて取得しています。
カ 電子帳簿保存法
税法上、契約書、注文書、領収書、見積書等の取引情報に係る書面は、7年間保存する義務があります(法人税法施行規則59条ほか)。
・ただし、電子契約のように電子データで保存する場合、以下の要件を満たすことで、紙の契約書等の原本と同等に扱われ、長期保存にかかる負担を解消できます(電子帳簿保存法10条)。
① 真実性の確保
認定タイムスタンプを付与、改変不可能若しくは改変が記録されるクラウドサービスを利用、又は社内規程があること。
② 関係書類の備付
マニュアルが備え付けられていること。
③ 検索性の確保
主要項目を範囲で指定及び組み合わせで検索できること。
④ 見読性の確保
納税地で、画面とプリンターで契約内容が確認できること。
キ 電子契約の導入メリット
これまでの書面による契約を電子契約に切り替えることで、企業は大きく3つのメリットを受けることができます。
① コスト削減
印紙代、郵送代、封筒代、インク代、人件費、保管費用が削減できる。
② 業務効率化
文書を紙面に印刷するなどの手間や保管先から検索する手間が削減できる。
③ コンプライアンス強化
原本の紛失や劣化、改ざん等のリスクが低減できる。
ク 電子契約導入に当たって注意点
電子契約の導入にはいくつか注意していただきたいポイントもあります。
① 法律で書面が求められる契約類型が一部に存在する。
電子契約が普及している中でも、消費者保護などを目的として、法律で書面(紙)による締結や交付が義務付けられているものも、一部ですが存在します。
* 法律で、書面(紙)による締結や交付が義務付けられているものの代表例
(ⅰ) 訪問販売
(ⅱ) 電話勧誘販売
(ⅲ) 連鎖販売
(ⅳ) 特定継続的役務提供
(Ⅴ) 業務提供誘引販売取引における交付書面(特定商品取引 法4条ほか)
② 受信者側(契約相手方)に手間やコストが発生する場合がある。
自社で導入できたとしても、電子契約の受信者側の理解も必要になります。相手が合意することで契約は締結されますので、受信者である相手が電子契約を拒んで従来の書面による契約を希望した場合は、相手に合わせなければならないケースも少なくありません。
・この点、事業者署名型(立会人型)を採用するクラウドサインでは、受信者は利用規約を確認いただくだけで、登録費用等は必要ありません。契約の相手方に負担を強いることなく、スピーディに契約を締結することができます。
ケ デジタル・IT用語の説明
① 電子ファイル
書類などを画像データとしてシステムに取り込み、検索できるようにしたデータのまとまり。
② インターネット
世界規模の通信ネットワーク。
③ サーバー
ネットワーク上で、他のコンピュータに対して各種のサービスを提供するコンピュータやソフトウエア―など。
④ クラウド(クラウドコンピューティング)
インターネット経由で提供されるコンピュータ資源やサービスを利用することで、様々な処理や機能を実現すること。
⑤ クラウドサービス
クラウドコンピューティングによって提供されるサービスの総称。
⑥ クラウドストレージ
クラウドの記憶装置。
⑦ データ
コンピュータが処理の対象とする情報。
⑧ コンプライアンス
要求や命令に従うこと。特に企業が法令や社会規範・企業倫理を守ること。法令順守。