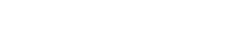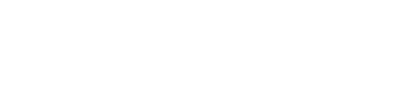私の好きな曲「ブラームス交響曲第4番」
冒頭のささやくようなヴァイオリンの旋律からたゆたうように開始される男の独白は、内省的でデリケートな歌を口ずさみ、ともすれば自暴自棄になりかねない感情の炸裂も、冷静さと秩序を保ちながら、最後は揺るぎなく、あまりにも決然としたフィナーレを迎える。
私が好きなブラームスの交響曲第4番。それは私小説のようであり、ひとりの男―あえてここは「男」と言い切りましょう―の告白を聞くかのようでもあります。
秋になるとブラームスが聴きたくなるということは、以前も当ブログで書きましたが、今年も変わりなくブラームス三昧の毎日です。特に今年は交響曲第4番に惹かれ、手持ちのCDやレコードをあれやこれやと持ち出し、取っ替え引っ替え聴いています。
ブラームスには4曲の交響曲がありますが、おそらくはその中で最も渋いこの第4番。ブラームス51歳の頃の作品です。作曲当時の時代背景からすると、多分に保守的、はっきり言ってしまえば古臭い音楽として、対立するワーグナー派にはもちろんのこと、親子ほど年の離れた後輩作曲家マーラーにも「空っぽな音の桟敷」と酷評されたとの記録が残っています。
現在では古典的な技法が用いられた円熟の傑作として、多くの演奏、録音の機会に恵まれているため、先に述べたように私もさまざまな演奏でこの曲を楽しむことが出来ています。
最近代わる代わる聴いているのは、CDでベーム指揮ウィーン・フィル、カラヤン指揮ベルリン・フィル(70年代)、バーンスタイン指揮ウィーン・フィル、スイトナー指揮シュターツカペレ・ベルリン、シャイー指揮ゲヴァントハウス管弦楽団、レコードでカラヤン指揮ベルリン・フィル(60年代)。そして、あえて日常的には聴くことを控えているクライバー指揮ウィーン・フィルのレコードに一度だけ針を落としました。
クライバー盤は、私にこの曲の魅力を教えてくれた恩人のような存在であり、10代の終わり頃、それこそ毎日のように聴いた思い出の詰まった1枚です―当時聴いていたのはCDであり、レコードは後日手に入れたものですが―。ブラームス後期の作品であり、諦念の表れとも言われる第4番―ベーム盤はまさにそのような演奏―を、録音当時50歳だったクライバーは、颯爽と、一点の曇りもなく、澄み切った秋の空のように奏でます。
個人的な思い入れが深いクライバー盤は、私の場合、曲を聴くというより、どうしても「思い出を聴く」というセンチメンタリズムに傾きがちです。それゆえ、日常的に聴くことを避けているのですが、久しぶりにターンテーブルにのせたクライバー盤は、力強く前向きで、明日が希望に満ちていることを確信させてくれる演奏でした。
今朝のお供、
AC/DC(オーストラリアのバンド)の『LIVE AT THE DONINGTON』。
R.I.P.マルコム・ヤング
(佐々木 大輔)