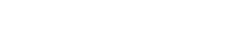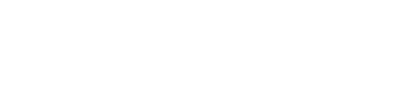村上春樹の物語とメタファー
―村上春樹とは、読む度、好きと思ったり嫌いと思ったり、アンビバレント(愛憎こもごも)な感情を抱く存在である―
今年2月に発表された村上氏の『騎士団長殺し』を読む準備運動として、村上氏の初期作品『風の歌を聴け』、『1973年のピンボール』、『羊をめぐる冒険』(以上、青春三部作)を再読しました。村上氏の作品は、大学生の頃に初めて読んで以来、折に触れて読み返しています。
今回の再読で最も考えさせられたのは、青春三部作の中では人気も世評も控えめな『ピンボール』。「僕」と双子の姉妹との日常、そしてデビュー作『風の歌』から続く「鼠」との友情を描いた作品です。双子の姉妹がどこからかやってきて、どこかへといなくなってしまったように、「僕」は物事に執着することなく、ただ事実を受け流します。一方、「鼠」は街を出ていくことを決意します。
「鼠」は「僕」の分身であり、社会にコミットメント(関与)出来ないでいる「僕」が生み出した「僕のあるべき姿」ではないか、と私は考えます。
一般的に村上作品の登場人物は、物事にかかわりをもたず無関心であること(デタッチメント)を特徴とし、それが人間関係や社会に縛られたくないと思っている人々の共感を呼んでいるところもあるかと思うのですが、私が、「僕」は社会にコミット「しない」のではなく「出来ない」のだと感じるのは、本作における「鼠」の決断に至る葛藤が、失うことを恐れて決断出来ない「僕」の葛藤として映るからです。「僕」自身、変わらなければならないことを分かっているんじゃないのかな。
実際、村上作品は、『ねじまき鳥クロニクル』で「デタッチメントからコミットメントへの転換」があり、その姿勢は、地下鉄サリン事件を扱ったノンフィクション『アンダーグラウンド』、阪神大震災を契機とした連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』に顕著です。
このような過去の作品とのつながりも考えながら、いよいよ最新作『騎士団長殺し』に突入。
果たして村上氏が本作で紡いだ物語は魅力的であったでしょうか。
残念ながら私は楽しめませんでした。それゆえ「私の好まない村上春樹」ばかりが目に付いてしまったようです。
謎の美少女、(井戸のような)穴と壁、都合のいい女性、お酒と料理と音楽・・・いつものレギュラーメンバー。
私の方が「やれやれ」と言いたい。
これらの「メタファー」を読み解くことが村上作品を読む楽しみであることは理解できます。しかし、その謎解きを楽しめるほど夢中になれなくなったのは、私が社会にコミットする立場にあり、(デタッチメントを脱したとはいえ)社会性の乏しい登場人物らに共感できなくなってしまったからかもしれません。
とはいえ、以上はあくまでも「物語」についての感想。
本作を通じて村上氏は何を語りたかったのか。
これについては私なりに感じるところがあり、深く考えさせられたことも事実。だからこそ、冒頭のアンビバレントな感情を抱きつつ、村上氏の作品から目が離せないのです。
今朝のお供、
ショルティ指揮ウィーン・フィルの演奏によるR.シュトラウスのオペラ『ばらの騎士』。
(佐々木 大輔)